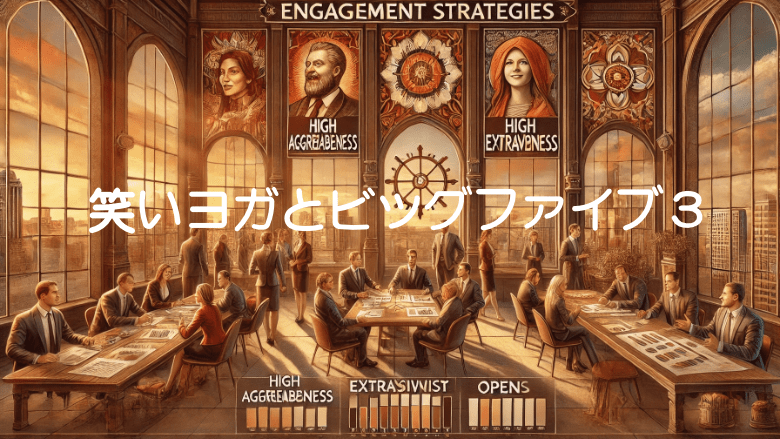「日常的な利他性とパーソナリティ特性がホスピタリティに及ぼす影響」というタイトルの心理学研究論文です。
ホスピタリティ(おもてなし)が、日常的な利他行動(人のために何かする行動)や、
ビッグファイブ(Big Five)性格特性とどう関係するかを探る。
特に、「日本型ホスピタリティ尺度」における5つの因子(サービス提供力・歓待・顧客理解力・外見と謙虚・誠実)との関連を分析しています。
研究のきっかけ(背景や動機)
ホスピタリティ=スキルではなく、性格とか人間味
1. ホスピタリティ“サービス”とは違う?
- 一律に提供されるサービスとは違って、
ホスピタリティは「対価を超えた、臨機応変で個別対応のもてなし」とされている。 - でも、それを測る尺度(日本型ホスピタリティ尺度)はあるのに、
「じゃあ何がそれを生み出しているのか」はちゃんと研究されてなかった。
2. ホスピタリティ、“人の優しさ(利他性)”によるもの
- 「相手のために、見返りなしに動く」ような行動=利他性は、
人間が本来的にもっている性質。 - だったら、日常の利他的な行動と、
職場でのホスピタリティって、つながってるんじゃないか?と考えた。
3. 性格(ビッグファイブ)も関係ある?という仮説
- すでに外向性・調和性・誠実性などが接客職の適性として注目されてる。
- 同時に、性格と利他行動の関係も研究が進んでいる。
- だったら、「利他性」×「性格特性」で、
ホスピタリティの発揮傾向が説明できるのでは?
上記の疑問からこの研究が始まりました。
【調査方法】
- 対象者:サービス業従事者208人(男女各104人、年齢層は20代〜50代)
- 調査手段:インターネット調査(マクロミル)
- 使用尺度:
- ◼️ 日本型ホスピタリティ尺度(山岸・豊増 2009)
- ◼️ 対象別利他行動尺度(家族・友人・他人への行動を測定)
- ◼️ ビッグファイブ短縮版尺度(N・E・O・A・C)
上記の方法で調査されました。以下のような結果になっています。
【主な結果と考察】
1. 日常的な利他性の影響
- 家族・友人への利他行動が、すべてのホスピタリティ因子に有意な影響があること。
- 見知らぬ他人への利他性はホスピタリティにほとんど影響しない。
- ★これは「ホスピタリティ」は単なる「善意」ではなく、
関係性のある相手に向けた行動であることを示唆。
- ★これは「ホスピタリティ」は単なる「善意」ではなく、
2. 性格特性(ビッグファイブ)の影響
- 外向性(E):すべてのホスピタリティ因子に強い影響。特に「歓待」に顕著。
- 開放性(O):「サービス提供力」「顧客理解力」「誠実」に影響。創造性が必要な対応力に関連。
- 調和性(A):「歓待」「外見と謙虚」に影響。場の雰囲気づくりに関与。
- 誠実性(C):「外見と謙虚」に影響。自己抑制や身なりの整えに関連。
- 情緒不安定性(N):影響なし。
上記のような結果によると、知っている人にはホスピタリティが発揮されるけど、
知らない人には、発揮しないという結果に。
ホスピタリティという行動は、見ず知らずの人には発揮されにくく、
知っている人にこそ発揮されるという観点から、
見ず知らずの人に発揮できる場合も、私たちは体験しています。
発揮されるには、もしかすると、ビッグファイブが影響している。
それはどんな時、という疑問が湧いてきますが…
まとめると、ホスピタリティは「心からのサービス」でありながらも、
実は関係性のある相手への投資行動に近い側面があります。
外向性や開放性といったパーソナリティ特性が、
上記の結果により、ホスピタリティの質に関係するのではないかと、
考えることができます。
関係性のある相手への投資行動
なぜ「家族・友人への利他行動」がホスピタリティに強く関係するのか?
これに関しては、進化心理学の視点を取り入れると理解しやすいです。
利己的な遺伝子は(かなりのボリュームですが)、
進化心理学や進化生物学について語られています。
遺伝子がなぜ自分を残すために人間や動物を動かしているという視点から行動を説明している内容です。
機会があればご一読を。
1. 進化的に“得”になる相手への行動が残りやすい
- 人類は「協力することで生き残ってきた生物」です。
- その中でも「血縁者(=遺伝子共有)」や「長期関係の相手(=互恵性)」に対しては、
- 行動コスト<将来の見返り(安全・支援・子孫繁栄など)
- → 脳が「それ、やる価値あるよ」と判断しやすい。
- 家族・友人はまさにその対象。
2. 見知らぬ他人=“関係性の予測がつかない相手”
- 見知らぬ人に優しくすることは、「コスト回収できるか不透明」=進化的にはハイリスク。
- よって、ホスピタリティ(本来は“継続関係のなかでの工夫や対応”)とは結びつきにくい。
ホスピタリティとは何かを再定義してみると…
ホスピタリティ=「関係性を強化・維持しようとする、心ある働きかけ」
- つまり、単なる善意や“思いつきの親切”とはちょっと違う。
- 相手との「これから」に向けた気づかいや創意工夫がある。
- → だからこそ、関係性が予測できる相手(家族・友人・常連客など)に対して発揮されやすい。
しかし、先ほども少しお話しした、見知らぬ他人への利他行動や、
ホスピタリティもあるよね、という疑問が起こります。
そこのところについてお話を進めていきます。
見知らぬ他者への利他行動とホスピタリティ
「ビッグファイブの特性によっては、見知らぬ人にもホスピタリティ的行動を発揮できるのでは?」
これは“ポテンシャル”としての資質の話となってくるという前提でお話を進めていきます。
ビッグファイブ特性と“見知らぬ人へのホスピタリティ”
図にすると以下になります。
| 特性 | 発揮しやすさ | 内容 |
|---|---|---|
| 外向性 | ◎ | 相手が誰であれ積極的に関わりやすい。感情表現豊か、関係構築への欲求が強い。 |
| 開放性 | ○ | 初対面・多様な相手でも、柔軟な対応や創意工夫ができる。 |
| 調和性 | △ | 他者への配慮はあるが、関係構築前はやや慎重(無理はしない)傾向。 |
| 誠実性 | △ | 信頼される行動をとるが、ルールや安全枠の中で行動する傾向があるため、未知の相手には慎重。 |
| 情緒安定性(低N) | ○ | 感情的ブレが少ないため、見知らぬ相手にも落ち着いて親切に対応しやすい。 |
結論的には
▶︎ ホスピタリティはもともと「関係性に基づく社会的行動」
- 家族・友人・常連など、“未来のつながりが想定される相手”に発揮されやすい。
- これは「報酬を期待してる」というより、「つながりを大事にしたい」という人間の本能。
▶︎ ただし、ビッグファイブの特性が強く影響すれば、
関係性がなくても発揮できることがある。
- 外向性・開放性が高い人は、「相手が誰でも関わりたい」力を持っている。
- だからこそ、業種業態によりますが、採用や育成で“性格特性 × 関係性構築力”を見える化することが重要。
いかがでしたでしょうか。
研究では、利他行動については相手との関係性でホスピタリティが発揮されやすいとされています。
しかし、私たちはホスピタリティを他者から受けるという体験をしています。
つまり、見知らぬ人への利他行動が発揮される場合もあるということです。
その行動は、関係性構築のための投資行動であり、
その行動がビッグファイブ特性による影響を受けるのではないかという疑問が浮かんだため、
ビッグファイブの関連性についても、お話しさせていただきました。
特性により発揮しやすさの違いがあることもお話しさせていただきました。
つまり利他行動は関係性の質にも影響を受ける、ということが言えるかと思います。
次回はそこについても触れてお話を進めていきます。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
小田真弓・平石界(2015). 『日常的な利他性とパーソナリティ特性がホスピタリティに及ぼす影響』, 2025年4月4日アクセス.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/personality/23/3/23_193/_article/-char/ja/山岸友佳子・豊増哲雄(2009). 『ホスピタリティの構造:日本型ホスピタリティ尺度の作成』, 2025年4月4日アクセス.
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000025-I013410002443549