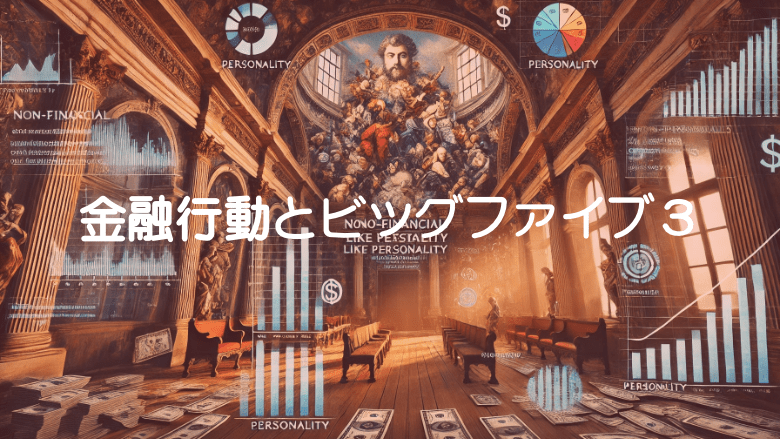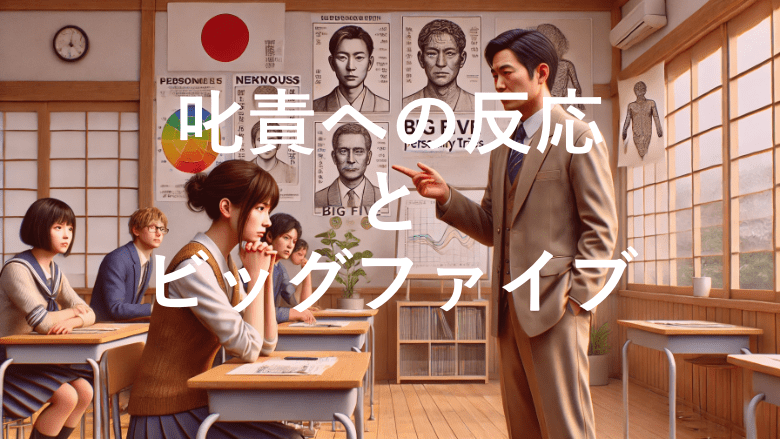前回はホスピタリティが発揮されやすい環境の基盤づくりについてお話を進めました。
またホスピタリティの発動にはOCBと同じ関係性の質も重要である等いうことです。
まずはホスピタリティを常態化するようにするにはを考えていきたいと思います。
ホスピタリティが発揮しやすい組織とは
LMXとTMXとOBSEの関係とは
LMXやTMXがあってOBSEが生まれるのか、
それともOBSEはLMXとTMXがないと生まれてこないか。
ホスピタリティは関係性構築のための投資行動であるということから考えると、
「信頼の連鎖構造」×「自己効力感の形成」という、
組織心理の根幹を問うめちゃくちゃ重要な論点であるからです。
OBSEは LMXやTMX“がないと”生まれないわけではないけど、
LMやTMの関係性が良好であるほど、OBSEは“育ちやすくなる”ということです。
OBSE(Organization-Based Self-Esteem)とは?
「私はこの組織にとって必要とされている」と、自分で思えているかどうか(=自己評価)
LMX・TMXとOBSEの関係性(先行研究ベース)では、以下のようになります。
| 関係性のタイプ | OBSEとの関係 |
|---|---|
| ◉ LMX(上司との信頼関係) | 強く正の相関:信頼される経験が「自分は大事にされてる」という感覚を生む |
| ◉ TMX(仲間との信頼関係) | 中程度の正の相関:支援や連携があると「チームの一員だ」と感じられる |
| ◉ OBSE(自尊感情) | 結果として形成される心理状態(自己内面) |
LMXやTMXが“なくても”OBSEは育つのか?
可能性としてはYES。ただし…
- たとえば:
組織文化(MVV・パーパス)が明確で、仕事が自己成長や社会貢献につながっていて、
自己効力感が高く、自律的に動ける人材であれば、
▶︎LMXやTMXが多少不十分でも、自分で「意味づけ」してOBSEを保つことは可能。
ただしこれは一種の“レアケース”であって、
大多数の人にとっては「関係性の質」がないと、OBSEは不安定になりがちです。
構造的に見るとこんな感じ:
◉
LMX/TMX(外的支援・関係性の質)◉
↓
◉OBSE(内的自尊感・効力感)
↓OCB・ホスピタリティ・主体的行動
OBSEを高めるには「関係性の見える化」と「MVVの浸透」がセットで必要ということが見えてきます。
「ホスピタリティが発揮される心理的土壌は何か?」
ホスピタリティは、TMX(仲間との信頼)とLMX(上司との信頼)の両方があり、
その中でOBSE(自分は役立っているという自尊感情)が育って初めて、
“本質的なホスピタリティ”が行動として発揮されるということです。
ホスピタリティとは?
- 相手への創意工夫と心ある行動
- マニュアルでは測れない「対価を超える」行動
- =つまり、「やらされている」ではなく“自らやりたいと思う行動”
ホスピタリティを引き出す3つの心理要素
| 要素 | 役割 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| ◆ TMX | 仲間との支え合い | 「みんなのためにやりたい」と思える“つながり”の感覚 |
| ◆LMX | 上司との信頼関係 | 「この人のために」「期待に応えたい」という“信頼”の感覚 |
| ◆OBSE | 自分への自信と誇り | 「自分の行動には意味がある」という“内面的な動機” |
逆に、これらがないと何が起こる?
- 「ホスピタリティ=サービス」になってしまい、“心”が抜け落ちる
- 「やれと言われたからやる」という“義務感”にとどまり、創意工夫がなくなる
- 「なぜ自分がやるのか分からない」状態になり、奉仕感はあるが喜びがない
つまり、“ホスピタリティという形”をなぞっているだけで、中身が伴わない状態になるというわけです。
ホスピタリティが本当の意味で発揮されるには、TMX・LMXによる“つながり”と、
OBSEによる“自分の存在価値の実感”が両方必要である。
ホスピタリティは他者との関係性を構築する投資行動。
関係性のある他者以外へ発揮するためには、
自分がいる組織の関係性の質が高くなければ、
自律的なホスピタリティへはつながらないということです。
つまり、「ホスピタリティ研修」だけしても、関係性と承認がなければ意味が薄く、
「ビッグファイブで適性がある人」を採っても、育つ環境がなければ発揮されない、
本質的には、“関係性の質こそがホスピタリティを支えるOS”である、
これをまず組織に根付かせることというわけです。
OCBとホスピタリティの違い
OCB(組織市民行動)】の特徴
定義:
OCBは、「職務の範囲を超えて、自発的に組織のために行う行動」を指します。
これには、上司や同僚、組織の運営に対する協力的な行動が含まれます。
- OCBは「組織に貢献するための行動」
- 組織やチームに利益をもたらす行動を自発的に行うことが主眼
- 評価されにくい、報酬を求めない場合が多い
具体的な行動例:
- 同僚を手伝う(利他性)
- 無理なく仕事を超えた部分をサポートする
- 上司に対して不満を表明しない(スポーツマンシップ)
目的:
- 組織の円滑な運営を助ける
- 報酬を求めるのではなく、職場の調和を維持することが目的
【ホスピタリティ】の特徴
定義:
ホスピタリティは、他者を歓迎し、心地よくさせるための行動や態度です。
特にサービス業において顧客に対するおもてなしが代表例ですが、人間関係全般における心のこもった配慮が広義にはホスピタリティに含まれます。
- ホスピタリティは「他者を心から歓迎し、気持ちよくする行動」
- 相手に対して**「温かさ」や「気配り」**を持って接する行動
- 積極的に感謝や敬意を示すことが含まれる
具体的な行動例:
- 顧客に対して、細やかなサービスを提供する(感情的な温かさ)
- 部下や同僚に対して親切に接する
- 相手の気持ちを理解しようとする行動
目的:
- 他者を心地よくさせることが最優先
- 企業やサービスのイメージ向上や顧客満足度向上を目指すことが多い
【OCB と ホスピタリティ の違い】
| 特徴 | OCB | ホスピタリティ |
|---|---|---|
| 目的 | 組織やチームのために、自発的に貢献する | 他者に心地よさや喜びを提供する |
| 主な行動対象 | 同僚、上司、組織 | 顧客、クライアント、同僚、友人 |
| 発動する動機 | 組織貢献や職場調和を意識 | 他者の満足や喜びを意識 |
| 目立つ特徴 | 無償の貢献、評価されにくい | 心からの歓迎、配慮、温かさ |
| 例 | 同僚を助ける、無理なく仕事をサポートする | 顧客に親切に接する、感謝を示す |
| 組織での影響 | 組織のパフォーマンスや効率の向上 | 顧客満足度や組織の評価向上 |
大事なポイント:
- OCBは「組織貢献」という枠組みの中で行動が発揮されますが、
ホスピタリティは他者(特に顧客)に対して提供する心のこもったサービスです。 - ホスピタリティは感情的な温かさが伴う点が特徴で、
相手の気持ちを中心に行動します。
OCBは、より「仕事の効率性」「チームワークの調和」に関わる側面が強いです。
この流れを図式化すると

ここまで見ると関係性の質が高まり、うまくいくようですが、
これだけでは足りないのです、それが、パーパスやMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)です。
これがないとただの“ごっこ”になってしまいます。
ホスピタリティが常態化するには
組織にパーパスやMVVVが浸透していることです。
しかし、研究では理念の浸透、パーパスやMVVが必要ということは語られていません。
ここに関係性の質には、パーパスやMVVが不可欠です。
なぜなら、これが組織の行動の基準となるからです。
理念ですよね。
ホスピタリティはOCBと同様の流れで生まれてくるものです。
この理念がないとホスピタリティやOCBはただのやらされている、
自律的が欠けてしまうからです。
従来のOCB(組織市民行動)理論の中では、「理念の共有」や「パーパスの浸透」は“前提条件”として明示的には扱われていませんでした。
理念の共有が語られてこなかったのか?
1. OCBは“行動”に焦点を当てた理論だから
OCB(Organizational Citizenship Behavior)は、 「報酬や評価を目的としない、組織を助ける自発的行動」
にフォーカスした理論であり、
「なぜその行動を取るか(価値観や理念)」よりも、
「どんな行動が取られているか」を分析することが目的でした。
2. OCBは“行動結果”、“動機の内面”が見えない
- OCBの分類(利他性、配慮、良心、市民的美徳など)は、 「観察可能な行動」や「結果」に基づいています。
- そのため、“なぜ人はその行動をするのか”という内的動機(理念・MVVなど)までは踏み込んでいない。
3. OCBは「組織文化」や「理念浸透」の前段階
- 組織開発(OD)や人的資本経営、パーパス経営の文脈でようやく、
「理念が行動にどうつながるか」が注目されるようになってきた段階です。 - OCB理論そのものは、90年代以前の管理心理学に基づいており、価値観共有や共通パーパスの話は未発展だった領域。
OCBとMVV(理念)をつなげる必要がある理由
| なぜ? | 今の時代的背景 |
|---|---|
| ◆ 多様性の中での協働 | “共通の価値観”がなければ、自発的行動(OCB)は分散・空回りしやすい |
| ◆ 自律と貢献が求められる | OCBを持続させるには「なぜそれをするのか」が必要=パーパスが動機になる |
| ◆ 再現性ある文化を作るには | MVVが“共通判断基準”としてなければ、OCBの“再現・称賛・継承”が難しい |
持続的かつ自律的行動を生むのは共通の思考
OCBやホスピタリティといった“善き行動”を持続的に引き出すには、
「MVV・パーパス」=「共通の思考の土台」が不可欠。
そして、それを支えるのが「関係の質」や「OBSE」。
関係の質とは下記のようなイメージです。

関係性の上にいろいろなものがのかっていて
関係性の質は高めれられていくのです。
ビジネスでは生産性の向上や売上向上につながる。
なぜなら、ビジネスは人が動かし、人がいないと動かないからです。
すっごくシンプルなんだけど、いろいろなものが積み重なり、
それらがしっかりと土台に根付くと、関係性の質の向上へとつながるのです。
OBSEも組織内で発揮されるにはという内容を次回はお話ししていきます。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
小田真弓・平石界(2015). 『日常的な利他性とパーソナリティ特性がホスピタリティに及ぼす影響』, 2025年4月4日アクセス.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/personality/23/3/23_193/_article/-char/ja/山岸友佳子・豊増哲雄(2009). 『ホスピタリティの構造:日本型ホスピタリティ尺度の作成』, 2025年4月4日アクセス.
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000025-I013410002443549乗松未央・木村裕斗(2021).
『性格特性と職場環境の相互作用が若年就業者の組織市民行動に与える影響:組織内自尊感情による媒介効果に着目して』,
『産業・組織心理学研究』, 35巻2号, pp.151-166.
2025年3月23日アクセス.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaiop/35/2/35_235/_article/-char/ja/