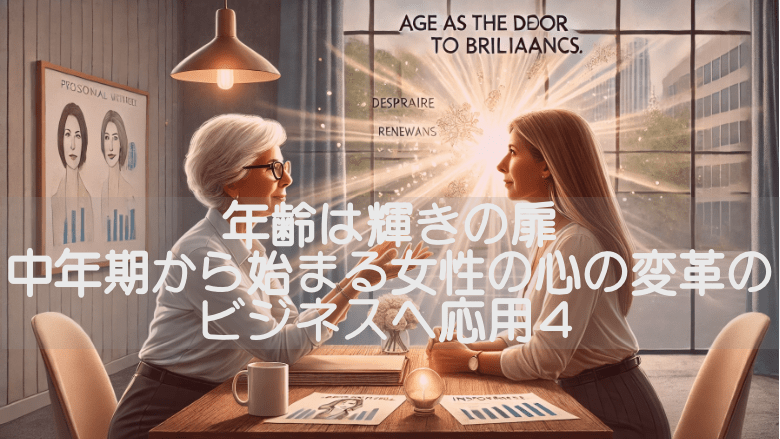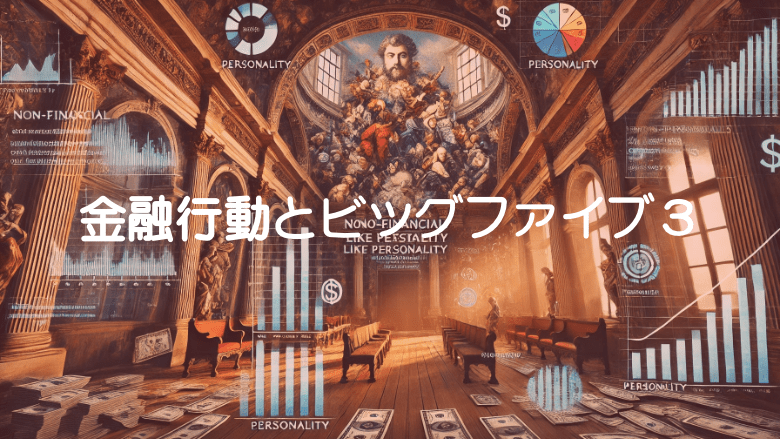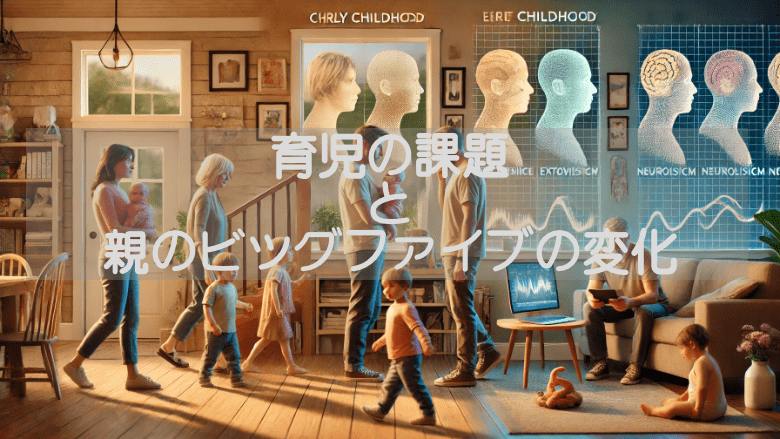前回はアイゼンクの性格理論と色彩診断にTOiTOiの3分類とビッグファイブ分析を加えたら、
どのような診断になるかを独断と偏見というやつでやってみました。
今回は研究調査した結果を現場で活かすとどのようになるかをみていきます。
研究結果を現場で活かすには
研究の結果が出ても、それが実際にどう応用されてるか?活用されてるか?
ってとても重要ではないでしょうか。
この論文(医療福祉系大学生の色彩嗜好と性格特性の関連)は、
結論で「新たな視点を提供する」と述べてはいますが、
実際の活用例や導入事例は明記されていません。
ただし、応用可能な具体的領域やアイディアは、
研究内容から読み解くことができます。
推察される応用例(この研究が活かされるシーン)
① 学内教育・キャリア支援
- 学科ごとの気質傾向(例:言語聴覚=黒胆汁質傾向)を活かす
- 個別サポート計画(メンタル不安傾向の早期対応)
- 実習前のカウンセリング内容を調整
- 性格と色嗜好を切り口にしたアイスブレイクや「自己理解ワーク」に展開
② 臨床実習での指導アプローチ
- 黒胆汁質の傾向が強い学生には、「不安への共感+丁寧な手順説明」が有効
- 多血質傾向の学生には、「ポジティブフィードバックと挑戦機会」で伸ばす
③ 医療職教育における多職種連携(チーム医療)
- 学科ごとの気質特性を把握することで、連携演習(チームケア・多職種協働)における役割分担や支援の仕方を調整
- 例:リーダーは多血質(外向・社交的)タイプに任せる
- 記録や手順確認は黒胆汁質(慎重・几帳面)タイプに適性あり
④ 「色と性格」の組み合わせを用いた教育コンテンツづくり
- 色カードを使った「気質診断」「コミュニケーションタイプチェック」
- 学生向け「色で見るわたしの性格傾向」ワークシート
- 実習指導者研修での導入(学生理解ツール)
応用イメージ(if こんなシーンで使える)
| シーン | 応用例 |
|---|---|
| オリエンテーション | 色嗜好診断で、学生同士の相互理解ワークを実施 |
| 実習前の面談 | 色×気質で不安傾向を事前把握、メンタルサポートへ |
| キャリア教育 | 性格傾向×色から、自分に合う職場環境や働き方を考える |
| 臨床指導者研修 | 色嗜好から学生の特性を把握→指導方針に反映 |
| チームケア演習 | 色をもとに「自分の役割」を気づかせる演習として活用 |
現状の課題
この研究のような「色×性格×教育」の知見は、実はまだ体系化・ツール化されていない領域。
つまり…
現場でどう使うかは、実践者の手に委ねられてる状態。
ということです。
私はTOiTOiというツールを持っているので、
類型論と特性論を合わせた、分析方法を考えたのですが、
ここでは類型論のみの方法を進めていきます。
類型論と特性論の分析方法
1. 各理論の役割整理
| 領域 | 理論 | 何がわかる? | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ◉タイプ | アイゼンクの4気質 | 大まかな気質傾向(内向・外向×不安定・安定) | わかりやすい性格分類 |
| ◉特性 | ビッグファイブ(OCEAN) | 外向性・協調性・誠実性・開放性・神経症傾向のスコア | 精緻な性格プロファイル |
| ◉感覚 | 色彩嗜好 | 感情傾向・心理状態・価値観 | 無意識・感覚的な自己理解の入口 |
2. 統合マトリクス(4気質 × OCEAN × 色)
| アイゼンク気質 | 主なOCEAN特性 | 好まれる色の傾向 | 特徴・行動傾向 |
|---|---|---|---|
| 多血質(陽気・社交的) | E↑、O↑、N↓ | 赤、ピンク、オレンジ、黄 | 明るくポジティブ、人とのつながりを求める。新しいことに前向き。 |
| 胆汁質(情熱・短気) | E↑、N↑、C↑ | 赤、黄、オレンジ | 主張が強くリーダーシップあり。怒りやすさもあり。 |
| 黒胆汁質(内向・繊細) | E↓、N↑、C↑、O↑ | 青、紫、水色 | 真面目で内省的。不安傾向も高く、感受性に優れる。 |
| 粘液質(穏やか・協調) | E↓、N↓、A↑、C↑ | 緑、茶、水色、黄緑 | 優しく控えめ。安定した環境や人間関係を求める。 |
3. どう統合的に分析するの?
① 色嗜好 → 無意識の傾向(ウォームアップ)
好きな色から、今の感情傾向や価値観を引き出す
② アイゼンク気質 → 性格の全体像
外向性&神経症傾向の組み合わせから、感情反応スタイルを大きく把握
③ ビッグファイブ → 特性の強度
外向性E・神経症傾向Nだけでなく、誠実性Cや協調性Aも加えて深堀り
🔍 4. 統合分析:例で見てみよう
ある人の結果
- 好きな色:青・紫・ピンク
- アイゼンク分類:黒胆汁質(内向・不安高め)
- OCEANスコア:
- E(外向性):低め
- N(神経症傾向):高め
- C(誠実性):高い
- A(協調性):中〜高
- O(開放性):やや高め
→ どう解釈する?
💡解釈例:
この人は「誠実で、繊細な感性を持ちつつ、社会性はやや控えめ」なタイプ。
好きな色(青・紫)が「知性・内省・個性」を反映しており、色と性格傾向に一貫性あり。
ピンクが混ざってる=実は「人とつながりたい気持ち」も秘めてるかも!
といういうような結果になるわけです。
類型論のみの場合
コンセプト:「色からわかる、わたしの性格傾向」
- 自己理解の“最初の一歩”として、色の好みを入り口にする
- 既存の分類(3タイプ、4気質、OCEAN)にとらわれず、色ごとに個性を掘り下げる
構成案:3ステップワーク
STEP1|好きな色を選ぼう(最大4色)
Q1. 今のあなたが“好き”と感じる色を、4つまで選んでください。
🟥 赤 🟧 オレンジ 🟨 黄 🟩 緑
🩵 水色 🟦 青 🟪 紫 🟫 茶
💗 ピンク 🟩 黄緑
→ 選んだ色から「個性キーワード」が表示される
STEP2|色がもつ心理的メッセージを知ろう
| 色 | キーワード | 性格傾向(抜粋) |
|---|---|---|
| 赤 | 情熱・行動・主導権 | エネルギッシュで自分の意見を持つタイプ |
| オレンジ | 社交・陽気・自由 | 明るくポジティブで周囲との関係性を大切にする |
| 黄 | 好奇心・楽観・知的探究 | 新しいことに敏感で、自分の考えを発信したいタイプ |
| 緑 | 安定・安心・自然体 | 調和や安心を大切にし、マイペースに進みたい人 |
| 水色 | 癒し・柔らかさ・平和 | やさしくて空気を読める、思いやり深いタイプ |
| 青 | 誠実・冷静・探究 | 筋を通したい、信頼されることに価値を感じる人 |
| 紫 | 感受性・個性・美意識 | 他と違う自分でいたい、感性が豊かなタイプ |
| 茶色 | 安定・実直・落ち着き | 安心できる日常が好き、地に足のついた性格 |
| ピンク | 愛情・共感・かわいらしさ | 愛されたい・守られたい・優しさに共鳴する人 |
| 黄緑 | 素直・若さ・可能性 | まっすぐで伸びしろがある、柔らかく変化に強い |
STEP3|あなたの傾向をまとめてみよう
選んだ色のキーワードを組み合わせて、あなたの現在の性格傾向を言語化してみよう。
ワーク記入欄(例)
- 今の私に多いキーワード:_____
- このキーワードから連想される「私の強み」:_____
- このキーワードから気をつけたい点は?:_____
- 一緒にいると相性が良さそうな人は?:_____
分析方法:どう読み取るか?
▼ ① 色のカテゴリを軸にタイプの傾向を読む
| 色の傾向 | 性格パターン |
|---|---|
| 暖色(赤・橙・黄・ピンク) | 外向的、ポジティブ、即行動型 |
| 寒色(青・水色・緑) | 内向的、慎重、安定志向 |
| 中性色(紫・黄緑・茶) | 独自性、調和志向、地に足の着いた |
選んだ色のバランスが、「あなたが今どんな性格バランスにあるか」を表す指標になる。
▼ ② グループワーク・フィードバックでの使い方
- 同じ色を選んだ人同士でシェア
- 「なぜその色が好き?」を問いかけると、
価値観の共有→自己理解→他者理解へ展開できる - 色ごとにフィードバックカードや解説シートを用意すると、セルフ解釈も可能
★ このスタイルのメリット
- タイプにラベリングされない安心感(多様性OK!)
- “今の自分”の感情状態や価値観を自然に言語化できる
- 色彩心理の応用で、感性×理性のバランスも読み取れる
上記のような流れ診断ワークが可能になります。
診断を現場で活かすにはということでお話を進めました。
利用できる場面がいろいろあると感じます。
類型論での診断となるので、
アイスブレイクの一つの手段としての利用が最適だと個人的に感じています。
最初のつかみ、ファーストインプレッションがとても大切ですので、
この診断はとても有効なのではないかと思います。
類型論だとタイプだけなので、深く立体的な診断は難しいです。
特性論を合わせることで、さらに使える場面が増えてきます。
今ある使えるもので、人を知る方法を研究するという点で、
この研究調査は有意義なものであると、感じています。
私たちが普段目にしているものって、このような研究調査が繰り返されて、
世に出されているわけです。
もっと世の中を良くしたいと思う心が、イノベーションを起こしていくのかなって感じます。
あなたはどんな世の中にしたいですか。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
大石如香・石本豪(2020). 『医療福祉を学ぶ大学生の色彩嗜好と性格特性の関連』, 2025年3月20日アクセス. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsaj/43/3+/43_169/_pdf
大学生の色彩思考と性格診断4へつづく