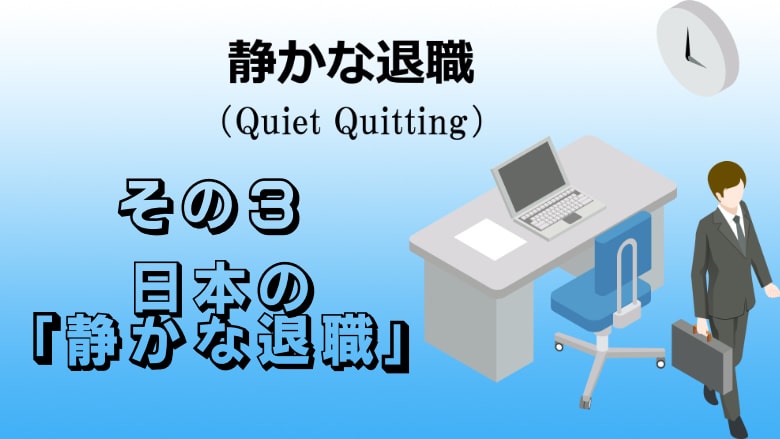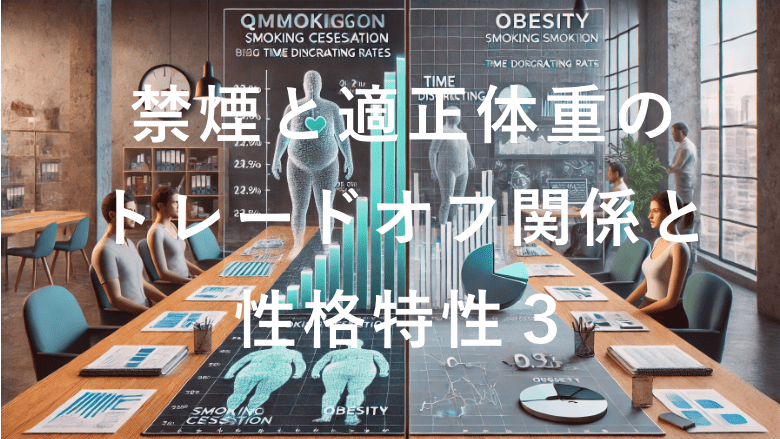親としての課題が親の性格形成にどのように影響を与えるかを調査した研究論文からのお話となります。
若年期および中年期における育児の課題と親の性格発達の双方向的関連について調査研究されています。
ここでは育児ストレスとビッグファイブの関連んいついてお話を進めていきます。
育児ストレスと親のビッグファイブ
目的
子どもを持つことが親の性格に与える影響を明らかにすることを目的に、
2つの研究を実施しました。
研究1: 新生児の母親(N=556)を対象に、育児の課題と性格発達の関係を調査。
研究2: 思春期の子どもを持つ母親(N=548)と父親(N=460)を対象に、
育児の課題と性格発達の相互作用を分析。
理論的背景
- 社会的投資理論
社会的役割(親、職業人など)への投資が、性格の成熟を促進するとされます。
この研究では、親という役割への取り組みが性格発達にどう影響するかを検証しました。
方法
- 研究1: ドイツの家庭データを用いた縦断調査(4年間)。
- 研究2: クロアチアでの親子の縦断調査(1年間隔で3回実施)。
結論
- 育児の課題を克服することが、
親の性格発達に寄与する重要なメカニズムである可能性が示唆されました。 - 若年期は性格変化が大きい一方、
中年期では変化が限定的であるものの、
親子関係が性格に影響を与えることが確認されました。
研究の詳細について見ていきます。
研究1の詳細
この研究では、新生児を持つ母親に焦点を当て、
育児のストレスが母親のビッグファイブ特性の変化に与える影響を分析しました。
研究目的
本研究の目的は、
出産後の育児ストレスが母親の性格変化(特に成熟度に関連する特性)にどのような影響を与えるかを検証することです。
従来の心理学では、性格は比較的安定していると考えられてきましたが、
近年の研究では、
社会的役割(仕事や親としての役割など)への適応が性格の変化をもたらす可能性が示唆されています。
この研究では、特に以下の3つの特性(成熟性の指標)が育児ストレスによって影響を受けるかを検証しました。
- 協調性(Agreeableness)
- 他者との協力や共感的な行動を示す傾向
- 誠実性(Conscientiousness)
- 計画性や責任感、自己制御を示す傾向
- 情緒安定性(Emotional Stability)(神経症傾向(Neuroticism)の反対)
- 感情の安定性とストレス耐性
仮説
- 育児ストレスが高い母親ほど、これらの特性(協調性・誠実性・情緒安定性)が低下する
→ ストレスによって、共感的な行動や責任感が低下し、感情の安定性も損なわれると予測。
研究デザイン
データセット
この研究は、
ドイツの社会経済パネル研究(German Socio-Economic Panel Study, SOEP)を用いた縦断研究(longitudinal study)として実施されました。
- 対象者: 2006年~2009年に出産した625人の母親
- 最終分析に含まれた人数: 556人の母親
- 2005年(出産前)の時点で性格特性データを提供
- 2009年(出産後4年)の時点で再び性格特性データを提供
- 年齢層: 19歳~45歳(平均31.5歳)
測定
1. 育児ストレス(Parenting Challenges)
- SOEPの「母親と子どもの質問票(Mother and Child Questionnaire)」を使用
- 育児ストレスを測定する3つの項目(4段階評価):
- 「疲労感が強く、気力が尽きることが多い」
- 「育児の責任をこなすのが難しいと感じる」
- 「母親としての役割に縛られていることが辛い」
- 内部整合性(信頼性): α = .59(やや低め)
2. 性格特性(Big Five: 協調性・誠実性・情緒安定性)
- ビッグファイブインベントリ(Big Five Inventory, BFI)の短縮版(15項目版)
- 7段階評価(1 = 全く当てはまらない, 7 = 完全に当てはまる)
- 各特性の内部整合性:
- 協調性: α = .52(やや低い)
- 誠実性: α = .64(中程度)
- 情緒安定性: α = .59(やや低い)
- 性格測定の時点
- 2005年(出産前)
- 2009年(出産後4年)
統計解析
- 潜在変数モデル(Latent Variable Modeling)を用いた縦断回帰分析
- 独立変数: 育児ストレス(2006年~2009年)
- 従属変数: 性格特性の変化(2005年 → 2009年)
- 統制変数: 年齢、社会経済的地位、学歴、パートナーの有無
- データ欠損:
- 欠損データは完全ランダム(Little’s MCAR test, p = .84)
- フル情報最大尤度法(FIML)で補完
研究結果
主要な発見
- 育児ストレスは、協調性・誠実性・情緒安定性の低下と関連
- 協調性の低下(β = -0.18, p < .05)
- 誠実性の低下(β = -0.19, p < .01)
- 情緒安定性の低下(β = -0.22, p < .01)
- 高いストレスを感じる母親ほど、出産後に性格の成熟度が低下
- 特に情緒安定性の低下が最も顕著
- ストレスが高いと共感性(協調性)が減少し、育児に対する忍耐力も低下
- 責任感(誠実性)の低下により、計画的に育児をこなすことが困難になる
- ストレスが強いほど、情緒が不安定になり、育児の負担をより大きく感じる
考察
1. 育児ストレスは「社会的投資理論(Social Investment Theory)」の逆効果をもたらす
- 社会的役割(親としての役割)への投資が人格の成熟を促進するという理論があるが、
ストレスが強すぎるとむしろ成熟が妨げられる可能性がある。 - 例えば、育児に困難を感じると、親としての役割への投資が減少し、
性格の成熟も停滞することが示唆される。
2. 性格の「変化」と「安定性」
- 以前は「性格は成人期に固定される」と考えられていた(Costa & McCrae, 1994)。
- しかし、環境要因(特に育児のストレス)によって、
成人後も性格が変化することが本研究から示唆された。
3. 母親特有の影響
- 父親データがないため、育児ストレスが父親にどのような影響を与えるかは不明。
- 母親に特有のホルモン変化(エストロゲン、オキシトシンの影響)や、
社会的期待(母親は「良い親」であるべきというプレッシャー)が影響している可能性もある。
結論
- 育児ストレスは、母親の性格発達に悪影響を与える
特に、協調性・誠実性・情緒安定性が低下 する傾向がある。 - 育児のストレスを軽減するサポート(パートナーの協力、社会支援、心理的ケア)が重要
- 育児を通じたポジティブな変化を促すための支援が、
母親の心理的健康に寄与する可能性がある
1. 協調性(Agreeableness)
- 新生児の母親(研究1)
- 育児のストレスが高いほど、協調性が低下 することが確認されました。
2. 誠実性(Conscientiousness)
- 新生児の母親(研究1)
- 育児ストレスが高いほど、誠実性が低下 することが判明。
3. 情緒安定性(Emotional Stability, またはNeuroticismの反対)
- 新生児の母親(研究1)
- 育児ストレスが高いほど、情緒安定性が低下(神経症傾向が高まる) することが確認されました。
この研究は、育児が親自身の性格発達に与える影響を初めて長期的に示した点で重要な意義を持っています。
育児に私的や公的な支援が不可欠ということがこの研究調査でわかっています。
こういった研究が政府までとは言えませんが、
企業内で共有されれば、また人事部で人財のプライベートな課題を共有することで、
社内活性化や離職ゼロ、人財の活躍へつながる施策検討の参考やヒントになるかと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
Hutteman, R., Bleidorn, W., Keresteš, G., Brković, I., Butković, A., & Denissen, J. J. A. (2014). 『若年期および中年期における育児の課題と親の性格発達の双方向的関連』, 2025年1月30日アクセス. https://doi.org/10.1002/per.1932
育児ストレスと親のビッグファイブの変化2へつづく