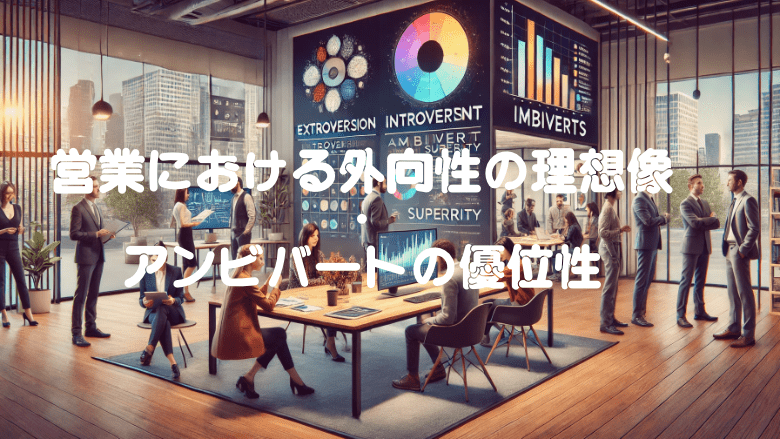前回は金融行動とビッグファイブ分析との関連について、
別の観点からお話を進めました。
ここでは機械学習の分類木(Classification Tree)を用いて、
銀行口座を持つ(Banked)か持たない(Unbanked)か
などを決定する際の性格特性の影響を分析した結果についてお話を進めていきます。
ビッグファイブ特性の影響
Figure 1 の詳細解説

Figure 1 は、機械学習の分類木(Classification Tree)を用いて、
銀行口座を持つ(Banked)か持たない(Unbanked)かを決定する際の性格特性の影響を分析した結果を示しています。
1. 図の構成
この分類木は、金融行動(銀行口座の有無)に関連するビッグファイブ性格特性を基にした意思決定の流れを視覚的に示しています。
- 「Neuroticism(神経質傾向)」を最初の分岐点として、
どの性格特性が銀行口座の有無に影響を与えるかを示しています。 - 「Extroversion(外向性)」が次の重要な分岐要因となっており、
銀行口座を持っているかどうかの決定に影響を及ぼしています。
2. 解析結果の解釈
この分類木は以下のように解釈できます。
- 神経質傾向(Neuroticism) < 2.3 の場合
- 銀行口座を持つ(Banked)可能性が高い
- → つまり、神経質傾向が低い人(ストレスや不安をあまり感じない人)は、
銀行口座を持つ確率が高い。
- 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.3 の場合
- 次に外向性(Extroversion) >= 3.5 の場合、
銀行口座を持つ(Banked)確率が高い。 - → つまり、神経質傾向が高くても、
外向性が高い(社交的な)人は銀行口座を持つ傾向がある。
- 次に外向性(Extroversion) >= 3.5 の場合、
- 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.3 かつ 外向性(Extroversion) < 3.5 の場合
- さらに分岐があり、外向性(Extroversion) < 2.6 の場合は銀行口座を持つ(Banked)可能性が高い。
- 外向性(Extroversion) >= 2.6 の場合は無銀行者(Unbanked)になる確率が高い。
- → つまり、神経質傾向が高く、外向性も中程度の場合は、銀行口座を持たない(Unbanked)可能性が高い。
3. 主な結論
- 最も重要な性格特性は「神経質傾向(Neuroticism)」
- 神経質傾向が高い(2.3以上)人は、銀行口座を持たない(Unbanked)可能性が高い。
- 逆に、神経質傾向が低い(2.3未満)人は、銀行口座を持つ確率が高い。
- 「外向性(Extroversion)」も重要な役割を果たす
- 神経質傾向が高くても、外向性が非常に高い(3.5以上)場合は、
銀行口座を持つ可能性がある。 - 神経質傾向が高く、外向性も低め(2.6以上)の場合は、
無銀行者(Unbanked)になる確率が高い。
- 神経質傾向が高くても、外向性が非常に高い(3.5以上)場合は、
4. 実務への応用
- 銀行口座を持たない人(Unbanked)のターゲティング
- 神経質傾向が高く、外向性が中程度の人は銀行口座を持たない可能性が高いため、
金融教育やサポートが必要。 - 例えば、「ストレスを感じやすい人向けの安心サポートプログラム」などを提供すると、
銀行口座の普及率が上がる可能性がある。
- 神経質傾向が高く、外向性が中程度の人は銀行口座を持たない可能性が高いため、
- 銀行サービスのマーケティング戦略
- 外向性が高い人には、ネットワーキングやコミュニティの要素を強調したサービスを訴求すると、
銀行口座を持つ確率が上がるかもしれない。 - 例えば、「新規口座開設で友人紹介キャンペーン」などが効果的。
- 外向性が高い人には、ネットワーキングやコミュニティの要素を強調したサービスを訴求すると、
- 金融リテラシー向上施策
- 神経質傾向が高い人はリスクを恐れる傾向があるため、
「安心・安全」を訴求した金融リテラシー教育が重要。 - 例えば、「リスクを最小限にするための銀行口座活用法」といった教育コンテンツが有効。
- 神経質傾向が高い人はリスクを恐れる傾向があるため、
5. まとめ
| 要因 | 銀行口座を持つ確率 |
|---|---|
| 神経質傾向(Neuroticism) < 2.3 | ⬆ 高い(Banked) |
| 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.3 かつ 外向性(Extroversion) >= 3.5 | ⬆ 高い(Banked) |
| 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.3 かつ 外向性(Extroversion) < 3.5 | ⬇ 低い(Unbanked) |
| 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.3 かつ 外向性(Extroversion) >= 2.6 | ⬇ 低い(Unbanked) |
この結果から、金融行動(銀行口座を持つかどうか)は、
性格特性に大きく左右されることが分かる。
特に、神経質傾向と外向性の組み合わせが決定要因となる。
Figure 2 の詳細解説

Figure 2 は、機械学習の分類木(Classification Tree)を用いて、
クレジットカードを持っているかどうか(Credit Card Adopter)を決定する性格特性の影響を分析した結果を示しています。
1. 図の構成
この分類木は、ビッグファイブ性格特性(Big Five Personality Traits)に基づき、
クレジットカードを持っているかどうかを決定するプロセスを示すものです。
- 最も重要な分岐点(最初の決定要因):
「Neuroticism(神経質傾向)」 - 次に影響を与える要因:
- 「Conscientiousness(誠実性)」
- 「Extroversion(外向性)」
2. 解析結果の解釈
この分類木は以下のように解釈できます。
- 神経質傾向(Neuroticism) < 2.1 の場合
- クレジットカードを持つ(Has credit card)確率が高い
- → 神経質傾向が低い(ストレスをあまり感じない)人は、
クレジットカードを持つ確率が高い。
- 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.1 の場合
- 次に誠実性(Conscientiousness) >= 4.3 の場合、
クレジットカードを持つ確率が高い。 - → 神経質傾向が高くても、誠実性が高い(計画的で責任感がある)人は、
クレジットカードを持つ傾向がある。
- 次に誠実性(Conscientiousness) >= 4.3 の場合、
- 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.1 かつ 誠実性(Conscientiousness) < 4.3 の場合
- さらに分岐があり、外向性(Extroversion) < 2.5 の場合はクレジットカードを持つ(Has credit card)確率が高い。
- 外向性(Extroversion) >= 2.5 の場合はクレジットカードを持たない(No credit card)。
- → 神経質傾向が高く、誠実性が低く、外向性も高い人は、
クレジットカードを持たない可能性が高い。
3. 主な結論
- 最も重要な性格特性は「神経質傾向(Neuroticism)」
- 神経質傾向が低い(2.1未満)人は、クレジットカードを持つ確率が高い。
- 神経質傾向が高い(2.1以上)人は、
追加の条件(誠実性や外向性)によってクレジットカードの所有が決まる。
- 「誠実性(Conscientiousness)」も重要な役割を果たす
- 神経質傾向が高くても、誠実性が高い(4.3以上)場合は、クレジットカードを持つ確率が高い。
- 誠実性が低い(4.3未満)場合は、外向性によって決定される。
- 「外向性(Extroversion)」が最後の分岐点
- 神経質傾向が高く、誠実性も低く、
外向性が高い(2.5以上)人は、クレジットカードを持たない確率が高い。 - 外向性が低い(2.5未満)場合は、クレジットカードを持つ確率が高い。
- 神経質傾向が高く、誠実性も低く、
4. 実務への応用
- クレジットカードを持たない人(No credit card)のターゲティング
- 神経質傾向が高く、誠実性が低く、
外向性が高い人はクレジットカードを持たない可能性が高いため、
クレジットカードの魅力を強調するマーケティングが有効。 - 例えば、「ストレスフリーなクレジットカード活用法」や
「安心して使える低金利プラン」などのプロモーションが有効。
- 神経質傾向が高く、誠実性が低く、
- クレジットカードサービスのマーケティング戦略
- 誠実性が高い人には、ポイント還元や長期的なメリットを強調したキャンペーンが効果的。
- 外向性が高い人には、「旅行特典」や「イベント特典」などのベネフィットを強調すると、
クレジットカードを持つ確率が上がる可能性がある。
- 金融リテラシー向上施策
- 神経質傾向が高い人はリスクを恐れる傾向があるため、
「クレジットカードの安全な使い方」や「不安を軽減する管理方法」の教育が重要。 - 例えば、「初心者向けのクレジットカード管理講座」や
「ストレスなく使えるクレジットカードの選び方」などの教育コンテンツが有効。
- 神経質傾向が高い人はリスクを恐れる傾向があるため、
5. まとめ
| 要因 | クレジットカードを持つ確率 |
|---|---|
| 神経質傾向(Neuroticism) < 2.1 | ⬆ 高い(Has credit card) |
| 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.1 かつ 誠実性(Conscientiousness) >= 4.3 | ⬆ 高い(Has credit card) |
| 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.1 かつ 誠実性(Conscientiousness) < 4.3 かつ 外向性(Extroversion) < 2.5 | ⬆ 高い(Has credit card) |
| 神経質傾向(Neuroticism) >= 2.1 かつ 誠実性(Conscientiousness) < 4.3 かつ 外向性(Extroversion) >= 2.5 | ⬇ 低い(No credit card) |
この結果から、クレジットカードを持つかどうかは、
神経質傾向・誠実性・外向性の3つの要因によって大きく左右されることが分かる。
特に、誠実性が高い人はクレジットカードを持つ確率が高く、
神経質傾向が高く外向性が高い人は持たない確率が高い。
Figure 3 の詳細解説
Figure 3 は、機械学習の分類木(Classification Tree)を用いて、
クレジットカードのリボ払い(Credit Card Revolving)を利用したかどうかを決定する性格特性の影響を分析した結果を示しています。
1. 図の構成
この分類木は、ビッグファイブ性格特性(Big Five Personality Traits)に基づき、
クレジットカードのリボ払いを利用するかどうかを決定するプロセスを示すものです。
- 最も重要な分岐点(最初の決定要因):
「Conscientiousness(誠実性)」 - 次に影響を与える要因:
- 「Neuroticism(神経質傾向)」
- 「Agreeableness(協調性)」
2. 解析結果の解釈
この分類木は以下のように解釈できます。
- 誠実性(Conscientiousness) >= 4.1 の場合
- リボ払いを利用しない(Revolve_1m_no)確率が高い
- → 計画的で責任感のある人は、クレジットカードのリボ払いを利用しない傾向がある。
- 誠実性(Conscientiousness) < 4.1 の場合
- 次に神経質傾向(Neuroticism) < 3.4 の場合、リボ払いを利用しない(Revolve_1m_no)確率が高い。
- → 誠実性が低くても、神経質傾向が低い(ストレスを感じにくい)人はリボ払いを利用しない傾向がある。
- 誠実性(Conscientiousness) < 4.1 かつ 神経質傾向(Neuroticism) >= 3.4 の場合
- さらに分岐があり、協調性(Agreeableness) < 3.3 の場合はリボ払いを利用しない(Revolve_1m_no)確率が高い。
- 協調性(Agreeableness) >= 3.3 の場合はリボ払いを利用する(Revolve_1m_yes)。
- → 誠実性が低く、神経質傾向が高く、協調性が高い人は、リボ払いを利用する確率が高い。
3. 主な結論
- 最も重要な性格特性は「誠実性(Conscientiousness)」
- 誠実性が高い(4.1以上)人は、
クレジットカードのリボ払いを利用しない確率が高い。 - 誠実性が低い(4.1未満)人は、追加の条件(神経質傾向や協調性)によってリボ払いの利用が決まる。
- 誠実性が高い(4.1以上)人は、
- 「神経質傾向(Neuroticism)」が次の重要な分岐点
- 誠実性が低くても、神経質傾向が低い(3.4未満)場合は、
リボ払いを利用しない確率が高い。 - 神経質傾向が高い(3.4以上)場合は、
さらに協調性のレベルによって決まる。
- 誠実性が低くても、神経質傾向が低い(3.4未満)場合は、
- 「協調性(Agreeableness)」が最後の分岐点
- 神経質傾向が高く、協調性も高い(3.3以上)人は、
リボ払いを利用する確率が高い。 - 協調性が低い(3.3未満)人は、リボ払いを利用しない確率が高い。
- 神経質傾向が高く、協調性も高い(3.3以上)人は、
4. 実務への応用
- リボ払いを利用しやすい人(Revolve_1m_yes)のターゲティング
- 誠実性が低く、神経質傾向が高く、
協調性が高い人はリボ払いを利用する可能性が高いため、
適切な金融教育が必要。 - 例えば、「賢いクレジットカードの使い方」や「リボ払いのリスクを軽減する方法」などの教育プログラムが有効。
- 誠実性が低く、神経質傾向が高く、
- クレジットカードサービスのマーケティング戦略
- 誠実性が高い人には、長期的なメリットを強調した低金利ローンを訴求すると、
リボ払いを避けるよう促せる。 - 協調性が高い人には、グループ割引や共同購入特典を提供することで、
賢い利用方法を推奨できる。
- 誠実性が高い人には、長期的なメリットを強調した低金利ローンを訴求すると、
- 金融リテラシー向上施策
- 神経質傾向が高い人はリスクを恐れる傾向があるため、
「リボ払いの仕組みとその影響」を明確に説明する教育が重要。 - 例えば、「リボ払いのシミュレーションツール」や
「リボ払いを避けるための管理方法」などの教育コンテンツが有効。
- 神経質傾向が高い人はリスクを恐れる傾向があるため、
5. まとめ
| 要因 | リボ払いを利用する確率 |
|---|---|
| 誠実性(Conscientiousness) >= 4.1 | ⬇ 低い(Revolve_1m_no) |
| 誠実性(Conscientiousness) < 4.1 かつ 神経質傾向(Neuroticism) < 3.4 | ⬇ 低い(Revolve_1m_no) |
| 誠実性(Conscientiousness) < 4.1 かつ 神経質傾向(Neuroticism) >= 3.4 かつ 協調性(Agreeableness) < 3.3 | ⬇ 低い(Revolve_1m_no) |
| 誠実性(Conscientiousness) < 4.1 かつ 神経質傾向(Neuroticism) >= 3.4 かつ 協調性(Agreeableness) >= 3.3 | ⬆ 高い(Revolve_1m_yes) |
この結果から、クレジットカードのリボ払いを利用するかどうかは、
誠実性・神経質傾向・協調性の3つの要因によって大きく左右されることが分かる。
特に、誠実性が高い人はリボ払いを避け、
神経質傾向が高く協調性も高い人はリボ払いを利用する確率が高い。
今回は非常に長いというか、冗長になってしまいました。ごめんなさい。
ただ、今回ご紹介した調査の目的が、「性格特性が金融行動をどこまで説明できるのか」という点を明らかにし、
教育・政策・商品設計などに応用するためのエビデンスを提供することにあったということ、
「性格という非金融的要因が実は金融リスク行動を左右する」ということをエビデンスとして、
ボストン連邦準備銀行が出したということにつきます。
日本での金融教育は遅れていることが原因であると、私は感じています。
やっと最近になり、金融教育が広まり始めています。
しかし、まだまだ立ち遅れている感は否めません。
今の政策から考えると、自分の財産は自分で守らなければならない。
国は頼っていては、いけないという危機感もあります。
タイムリーなお話だと、通勤手当にも税がかかるなんてお話がでています。
国のために税金を納めていても、また搾取されるそんな国にいてもなあと、
最近本当に感じています。
私たちの納めている税金がこの国を良くするために使われているのかと考えると、
使われていないような感じがとてもしています。
だったら、私たちは自分たちの財産を守れる金融知識を身につけないといけない。
先にも書いた性格分析という非金融的要因が金融リスクを避けるエビデンスとしてだされいます。
この結果を踏まえた金融リスク回避策を考えるきっかけになればと幸いです。
最後までご覧いただいた方、本当にありがとうございます。
参考資料
サリバン, R. & ヒッチェンコ, M.(2023). 『性格特性と金融成果(Personality Traits and Financial Outcomes)』, ボストン連邦準備銀行, 2024年3月19