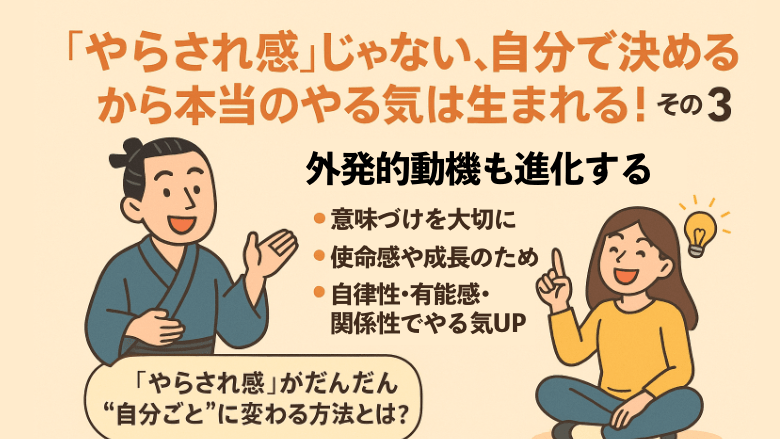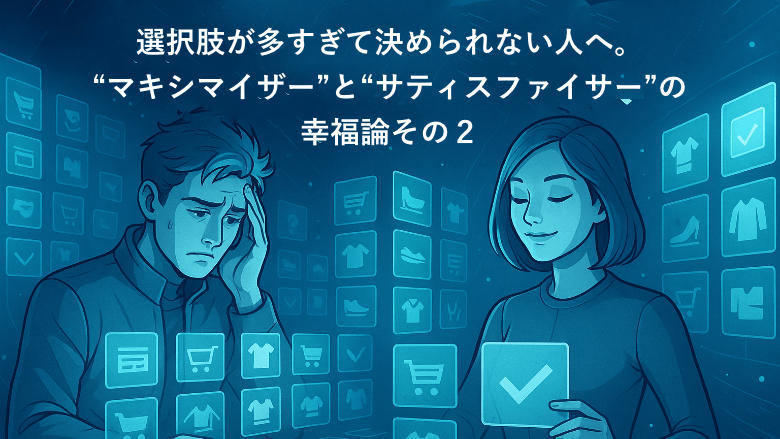やろうと思っても続かないことってありますよね。
例えば、ダイエットなんかしようと思ってやっても続かない、
なんてことは誰もが経験していることではないでしょうか。
今回はやる気についてお話をしていきたいと思います。
まずは“やる気”って何?から考えていきますね。
やる気ってなにか
やる気を引き出そうとすると、なぜか根性論的なことになってしまいます。
やる気についてある論争がありました。
1960~70年代、
職場やビジネスの現場では「やる気ってどうやって引き出す?」が大問題だった時代です。
お偉い先生方が叫びます、
「期待理論や!人は“がんばったら得する”と思えば頑張るんや!」、
「仕事には“やりがい”と“ご褒美”、両方用意しろ!」って…
みんな「やる気は“足し算”や!いっぱい盛ればみんなハッピー!」と信じられていた時代でした。
昔は「仕事=外からのご褒美(給料、昇進)で釣ればOK!」が主流だったけど、
これが意外と逆効果になる場面が多いって発見される。
そこで生まれてきたのが自己決定理論(SDT)です。
自己決定論は、「人は“やらされ感”より“自分で決めて動く”方が断然やる気出るんだぞ」って話です。
・内発的動機づけ(楽しい!面白い!自分でやりたい!)と、
・外発的動機づけ(ご褒美・評価・怒られたくない…)は、実は足し算じゃなくて、
外からの圧力が強すぎると「やる気スイッチ」がOFFになることもある。
「褒めて伸ばすって言うけど、褒めるのが“監視付き”だったら、逆にやる気なくなりますぜ親分!」ということなんです。
やる気とは“自分で決めて動く方が断然湧いてくる”のです。
また、やる気とは「目標の“内容(What)”と“動機(Why)”次第で、人生の楽しさもやる気もメンタルも変わっちゃうよ」
――という話です。
やる気を引き出す自己決定論とは
現代の心理学では「人は目標(ゴール)を目指して行動する」と考えます。
でも…
「同じゴール」でも「行き方次第」で結果が違う
目標の「中身(What)」も「動機(Why)」も大事です。
例えば…
「給料アップのために資格を取る」人と「自己成長のために資格を取る」人では資格と取るという同じ行動でも、
やる気や満足感が全然違うわけです。
SDTはDeciとRyanのコンビが提唱した理論で、
「人が本当に幸せに生きるためには3つの“基本的欲求(ニーズ)”が大事だよ」という内容です。
まずはSDTを提唱下2人の人物についてお話を進めていきます。
2人の巨匠
1. デシ氏(Edward L. Deci):やる気界の“名人”!
デシ氏はアメリカ生まれの心理学者。ロチェスター大学の名誉教授で、
若い頃から「人はなぜ動くのか?」をひたすら追いかけ続けた“やる気ハンター”なんです。
1971年の有名な実験で「ご褒美を与えすぎると人はやる気をなくす!?」という衝撃的な結果を発表し、
当時の学会をザワつかせた。
◆ デシ先生の“伝説パズル事件”
学生にパズルを解かせ、「ご褒美あり」組と「ご褒美なし」組でやる気を比較。
結果:ご褒美がなくなった瞬間、もらってた組だけ「やる気ゼロ」!
落語ネタ風に言えば…
「ご褒美で踊った猿も、エサが切れたら“あとは野となれ山となれ”やで!」と、
これが「外発的動機づけが強すぎると、内発的やる気を殺す」発見の原点!となるんです。
2. ライアン氏(Richard M. Ryan):SDT界の“参謀”!
アメリカの心理学者、同じくロチェスター大学の先生で、
デシ氏の“最強の相方”であり、SDTを一緒に作り上げたパートナーでもあります。
実証研究を重ね、「やる気と“自分ごと感”は世界中共通」ということを証明してきた理論派です。
◆ ライアン先生の“世界横断自己決定旅”
SDTを使って日本・アメリカ・ヨーロッパ・中国などで「やる気と自己決定」の研究を展開し、
教育・医療・スポーツ…あらゆる現場で「自律性・有能感・関係性」の三大欲求が大事だと証明しました。
たまに「サーフィンが趣味」と公言し、やる気と波乗りの関係まで研究した説(マジです)。
ご紹介した2巨匠がやる気ってなんなんだということを研究調査し、
こうしてやる気を高めるための方法を皆さんにご消化できております。
行動の質を変える3大ニーズ(Autonomy/Competence/Relatedness)
3つのニーズがあることで“やる気”がアゲアゲになり、
幸せを感じられ、行動の質を変える、なんていう素晴らしい発見でしょうか。
この3大ニーズをを見つけ出した2人の巨匠には私は感謝しかありません。
Deci & Ryanが言いたかったのは、「自分で選び、自分の意志で行動することこそが、
長期的な幸福感や達成感を生む!」ということ。
SDTの理論では、3つの基本的な心理的ニーズが、目標を達成するために必要不可欠だとしています。
その3大ニーズとは、以下のものです。
自律性(Autonomy)
自分で選択したいという欲求。他人に押し付けられた選択じゃなく、
自分の意志でやりたい!って気持ちが大事。
有能感(Competence)
「できた!」という感覚。何かを成し遂げた時に、
「自分でもできるじゃん!」と思える瞬間がモチベーションに。
関係性(Relatedness)
仲間とつながりを感じること。孤立していると、
どんなに頑張っても辛いだけ。チームや仲間の支えがあることで、
どんな仕事でも楽しくなる。
この3つが満たされると、やる気も幸福度もUP!
しかし、欠けると、「やらされ感」や「孤独感」でしょんぼり。
例えると「給食のない小学校」問題のようなものです。
昼ごはん抜きだと元気が出ないし、集中もできない。
でも給食が出てくると、「ワイワイ食べて」、
「自分でおかわり決めて」「完食して達成感」→勉強も遊びもやる気出る!
心の給食が「自律性・有能感・関係性」なんです。
私は落語をやっているので、落語のマクラ的に言うと、
「お客さん、“ニーズ”っちゅうのは、
腹が減った時のご飯みたいなもんで、“自律性・有能感・関係性”――
これが心の給食でございまして、
これを抜くと人間、どこかしらグーグー泣き出すんでございます。」
いかがでしたでしょうか。この3大ニースが満たされることで、
やる気が継続するというわけです。
昔やる気なかったら帰って言われたことを思い出しました。
やる気なかったら帰れって、それで帰ったら怒られるみたいな…
そんな話はどうでもいいですね。
“やる気”というのには他に大切なものもあります。
それは内発的動機を満たすということです。
次回は内発的動機についてお話を進めていきます。
最後までご覧いただきありがというございます。
参考資料
デシ, E. L. & ライアン, R. M. (2000). 『The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior』, 2025年7月1日アクセス.
https://www.academia.edu/76430355/The_What_and_Why_of_Goal_Pursuits_Human_Needs_and_the_Self_Determination_of_Behavior
“やらされ感”じゃない、“自分で決める”から本当のやる気は生まれる!その2へつづく