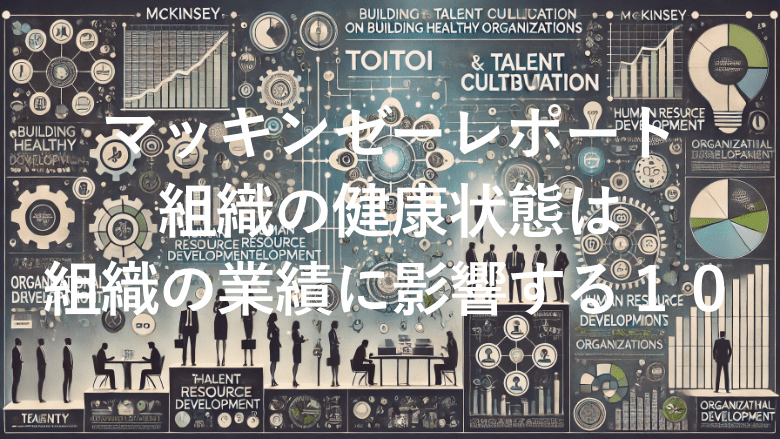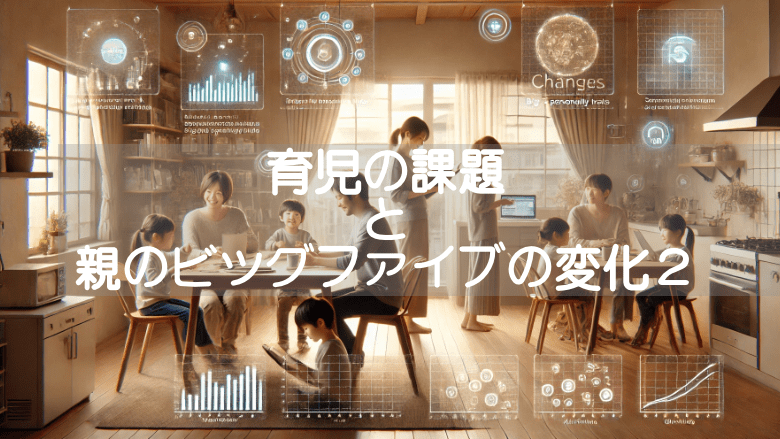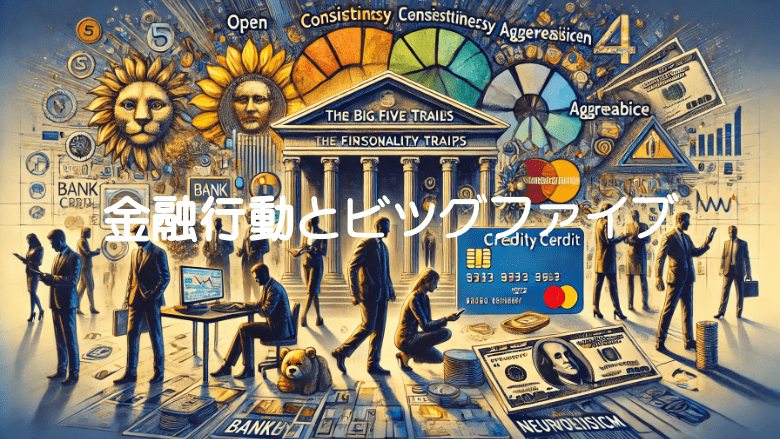日本におけるBig Fiveパーソナリティ特性(神経症傾向、外向性、開放性、協調性、勤勉性)と
BMI(ボディマス指数)の関連を調査した研究論文をご紹介します。
体の健康とビッグファイブ
1. 研究の目的
- 日本人を対象に、Big Fiveパーソナリティ特性とBMIの関連を分析する。
- 欧米や東アジアの既存研究と比較し、日本における特徴を明らかにする。
2. 調査方法
- 3つの大規模なデータセット(N = 3,063; N = 4,242; N = 17,471)を使用。
- 相関分析と重回帰分析を実施。
- さらに、過去の研究結果を統合するメタ分析を行い、日本における傾向を評価。
3. 主要な結果
- 勤勉性(Conscientiousness)はBMIと一貫して負の関連を示した(勤勉性が高いほどBMIが低い)。
- 外向性(Extraversion)は男性においてのみBMIと正の関連を示した(外向的な男性ほどBMIが高い)。
- その他の特性(神経症傾向、協調性、開放性)はBMIとの明確な関係を示さなかった。
1. 勤勉性(Conscientiousness)とBMIの負の関連:なぜか?
勤勉性が高い人ほどBMIが低いという結果は、心理学と健康科学の両面から説明できます。
(1) 健康行動の規律
- 勤勉性の高い人は、自己規律(Self-discipline)が強く、計画的な行動を取る傾向があります。
- これにより、食生活の管理がしっかりしており、過食を防ぎやすい。
- また、定期的な運動を習慣化する傾向がある(Bogg & Roberts, 2004)。
(2) 長期的な視点での健康管理
- 勤勉性が高い人は、短期的な欲求(例:高カロリー食品の摂取)を抑え、長期的な健康維持を優先する(Terracciano et al., 2009)。
- BMIが高くなるリスク要因(例:ジャンクフードの摂取、運動不足)を意識的に避ける。
(3) ストレスマネジメント能力
- 勤勉性が高い人は、計画的な生活を送り、ストレス管理が上手なため、ストレスによる暴飲暴食の影響を受けにくい。
- 逆に、勤勉性が低い人は、ストレス対処行動として過食に走る傾向がある(Sutin & Terracciano, 2016)。
(4) 睡眠の質との関連
- 勤勉性の高い人は規則正しい生活を送りやすく、睡眠の質も高い(Lodi-Smith et al., 2010)。
- 睡眠不足は食欲を増進させるホルモン(グレリン)の増加を引き起こし、BMIの上昇につながる(Elks et al., 2012)。
(5) 勤勉性と食行動
- 勤勉性が高い人は食事を規則的にとる傾向があり、食事のタイミングやバランスを意識することが多い(Sutin et al., 2015)。
- 勤勉性が低い人は、衝動的な食行動を取りがちで、カロリーの高い食品を無計画に摂取しやすい(Roberts et al., 2007)。
👉 総括: 勤勉性が高い人は、規則的な生活習慣、計画的な食行動、ストレス管理、運動習慣の維持ができるため、BMIが低くなりやすい。
2. 外向性(Extraversion)が男性のみBMIと正の関連を示した理由
外向性が高い男性はBMIが高い傾向があるが、女性ではこの関連がみられなかった。その理由を詳しく解説します。
(1) 外向性の高い男性は社交的な場面での食行動が多い
- 外向性が高い人は、人との交流を重視し、外食の機会が多い(Feiler & Kleinbaum, 2015)。
- 特に男性は飲み会や会食などの機会が多く、摂取カロリーが増える(Sutin et al., 2015)。
- 社交的な場面でアルコールや高カロリー食品を摂取する機会が増える。
(2) 男性の社会的ネットワークと飲食習慣
- 男性は女性よりも仕事関係の飲み会や会食に参加する割合が高い(厚生労働省, 2019)。
- 日本の社会では、特にビジネス環境において男性が飲食を伴う社交の場に参加する機会が多い。
- **「お付き合いの飲食」**という文化が根付いており、外向性の高い男性ほどその影響を受けやすい。
(3) 外向的な男性はエネルギー消費が多いが、それ以上に摂取カロリーが増える
- 外向性の高い人は活動的で運動量も多いが、
それ以上に食事や飲酒の影響が強いためBMIが上昇する(Brummett et al., 2006)。 - 特に男性は「大食い」や「お酒を飲むことが社交の一部」となりやすく、
結果としてBMIが上がる。
(4) なぜ女性ではこの関連が見られなかったのか?
- 女性の社交的な場面では、食事の量や内容に気を使う傾向がある(Pike & Dunne, 2015)。
- 女性は体型に対する社会的なプレッシャーが強く、ダイエット意識が高い(Otonari et al., 2012)。
- 外向性の高い女性も社交的ではあるが、食べる量を自己制御する傾向がある(Sutin et al., 2015)。
- 日本では、女性の方がカロリー摂取を抑えたり、ヘルシーな食事を選ぶ傾向が強い(北野 et al., 2014)。
👉 総括: 男性は外向性が高いほど社交の場で飲食の機会が増え、
BMIが上がりやすい。一方、女性は社交の場でも体型管理意識が働き、
過食を抑える傾向があるため、外向性とBMIの関連は見られなかった。
3. 他の特性(神経症傾向、協調性、開放性)がBMIと明確な関連を示さなかった理由
(1) 神経症傾向(Neuroticism)
- 一部の研究では、神経症傾向が高いとストレスによる過食が増える可能性があるとされている(Sutin & Terracciano, 2016)。
- しかし、本研究では明確な関連が見られなかった。
- その理由として、神経症傾向の影響がBMIに対して一貫した影響を与えない可能性がある。
- 神経症傾向が高い人の中には、ストレスで食べる人(BMIが増加)もいれば、
食欲を失う人(BMIが減少)もいる。 - 結果として、相反する影響が統計的に打ち消されてしまう可能性がある(Sutin et al., 2015)。
- 神経症傾向が高い人の中には、ストレスで食べる人(BMIが増加)もいれば、
(2) 協調性(Agreeableness)
- 協調性の高い人は他者との関係を重視するため、食生活も周囲の影響を受けやすい。
- しかし、その影響が必ずしもBMIの増減に結びつくわけではない。
- 家族や友人が健康的なら健康的な食生活を維持しやすいが、
- 周囲の食生活が不健康なら、それに影響されてしまう可能性もある(Sutin et al., 2015)。
- このように、協調性の影響は食生活に影響を及ぼすものの、
BMIの変化に明確なパターンを作らない可能性がある。
(3) 開放性(Openness)
- 開放性の高い人は、新しい経験を好むため食生活が多様化する可能性がある。
- しかし、それがBMIの増加や減少には明確に結びつかない。
- 例えば、開放性が高い人はベジタリアン志向を持つ人もいれば、
高カロリーな異国料理に興味を持つ人もいるため、影響が相殺される可能性がある。
👉 総括: 神経症傾向・協調性・開放性は、BMIに影響を与える要因を持つが、
その方向性が一定ではないため、明確な関連が見られなかった。
BMIの増加や減少がビッグファイブの因子と関連性するものとそうでないものがあることがわかりました。
また男女によっても違いがあることがわかったことはとても興味深い結果です。
あなたは健康に気を遣っていますか。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
吉野伸哉・小塩真司 (2020). 『日本におけるBig Fiveパーソナリティ特性とBMIの関連』, 2025年2月20日アクセス. https://doi.org/10.4992/jjpsy.91.19320
BMIとビッグファイブ分析2へつづく