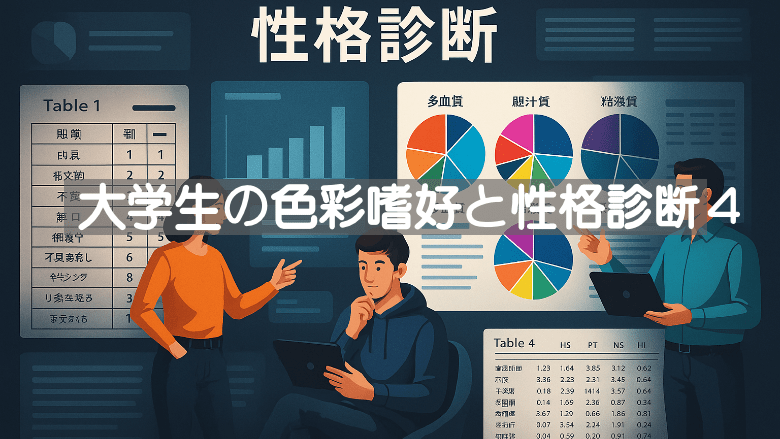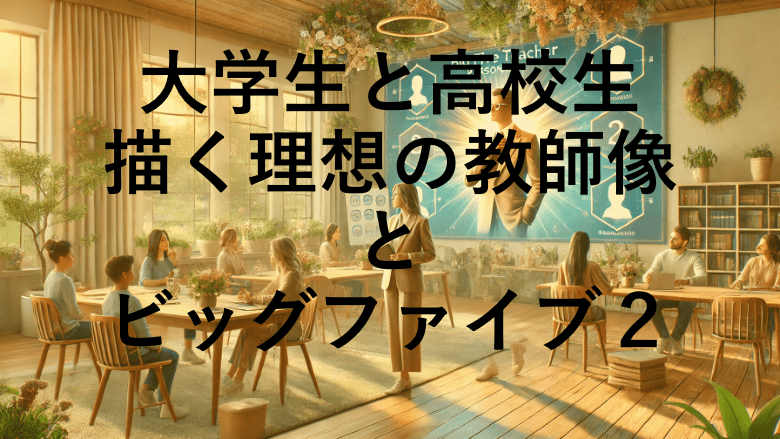新潟医療福祉大学の研究者による論文で、
大学生の「好きな色(色彩嗜好)」と性格特性の関係性を分析した内容になっています
それでは内容の詳細についてみていきます。
研究を行おうと思ったきっかけ・背景
◉ 教育現場での課題
- 医療福祉系の学生は将来、医療専門職として臨床現場に出るが…
- 実習指導者からよく指摘されるのは「コミュニケーション能力」や「社会性の未熟さ」
=これは「情意領域(態度・感情面)」に関する問題。
◉ 性格特性の理解が教育に重要
- 医療福祉系の大学では多様な職種(看護、理学療法、言語聴覚など)を目指す学生が在籍。
- それぞれの学生が持つ性格特性の違いを理解しないと、教育や指導にズレが出る。
◉ 色嗜好と性格の関連性に着目
- 過去の研究でも「パーソナリティと色の好みには関係がある」と指摘されている。
- ただし、学科別の違いや性格と色の関連をまとめた研究は少ない。
◉ 実用的な性格診断ツールを求めて
- これまで使われていた「YG性格検査(矢田部・ギルフォード)」は有料&時間がかかる。
- より簡単な性格検査(アイゼンクの4気質)を使って、色との関連を探りたいという動機がある。
「臨床実習での態度面の課題」→「学生の性格をもっと理解したい」→「性格と色の関係を調べよう」
という流れで、教育的実践ニーズから生まれた研究となっています。
なぜビッグファイブは使われていない?
本研究で使われているのは、以下の性格分類です。
▶ アイゼンクの性格理論(4気質分類)
- 黒胆汁質(内向・不安・まじめ系)
- 胆汁質(外向・情熱的・短気系)
- 多血質(陽気・社交的・活動的)
- 粘液質(おだやか・冷静・慎重)
つまり、古典的な類型論ベースであり、ビッグファイブのような特性論ではありません。
類型論(タイプ論)vs 特性論(トレイト論)
| 比較項目 | 類型論(タイプ論) | 特性論(トレイト論) |
|---|---|---|
| 主な考え方 | 性格は“いくつかのタイプ”に分けられる | 性格は“連続的な特性”で構成されている |
| 分類のしかた | 人を「〇〇型」「〇〇気質」に“分ける” | 各性格特性に“どのくらい強いか”で測る |
| 例 | アイゼンクの4気質/MBTI/エニアグラム/TOiTOi | ビッグファイブ/HEXACO/NEO-PI-R |
| 理論的な背景 | 哲学・精神医学からの伝統的ルーツが多い | 心理測定(心理統計・因子分析)に基づく |
| 用途 | タイプ別に理解・活用(教育、キャラ設定) | 性格の構成要素を定量的に把握(研究・採用) |
| メリット | わかりやすい!直感的!人に説明しやすい | 科学的!細かい個人差を表現しやすい |
| デメリット | 白黒つけすぎ・グラデーションが無視される | 数字での比較がやや難しく、直感性に欠けることも |
類型論(タイプ論)を詳しく!
◾️特徴:
- 人を一定の型に分けるアプローチ(YES/NOの分け方)
- 例:
・「あなたは黒胆汁質タイプです」
・「あなたは感性タイプです」
・「あなたはMBTIでENFPです」
◾️メリット:
- 一言で説明できる(セミナー、自己紹介、企業研修に強い)
- 共感しやすく、キャッチーに伝わる
◾️限界:
- グラデーションが見えない(両方当てはまる人への対応が難しい)
- タイプに当てはめすぎると「ラベリング」になりがち
特性論(トレイト論)を詳しく!
◆特徴:
- 人間の性格を数値や連続尺度で測るスタイル
- 例:
・外向性 82点、協調性 65点、神経症傾向 25点
・ビッグファイブ(OCEAN)が代表格
◆メリット:
- 個人差を定量的に把握できる(科学的・研究向き)
- 微妙なニュアンスの違いが拾える(同じ外向型でも強弱あり)
◆限界:
- 結果が数字中心で、ややわかりにくい
- 自己理解や他者理解に時間がかかることも
TOiTOi・ビッグファイブ・4気質の位置づけでみると…
| ツール | 分類 | 分類法 | メリット | 補完的な使い方 |
|---|---|---|---|---|
| TOiTOi | 類型論 | 感性/理性/比較 | 動機や価値観がわかる、研修やチームビルド向き | OCEANで強度を補足するとGOOD |
| ビッグファイブ | 特性論 | OCEANスコア | 科学的で個人差を細かく把握、採用や評価に有効 | TOiTOiでわかりやすい解釈に補完できる |
| アイゼンクの4気質 | 類型論 | 黒胆汁質などのタイプ分類 | 教育現場や自己分析入門にぴったり | 色嗜好や行動傾向との相性が◎ |
※TOiTOi(◀︎PDFのカタログがDLできます)は、Team Organaization Inventory ・組織編成分析の略語で、
組織の適材適所を科学的に分析し、
最適なチームをつくるツールです。
TOiTOiの由来はドイツ語で「幸運のおまじない」を意味するtoitoitoi、
相性を可視化し、働きやすい環境を実現するHRテックツールです。
TOiTOiには類型論である3分類(理性・比較・感性)と、
特性論であるビッグファイブが搭載されています。
◆現場活用でのおすすめスタンス
⚫︎ 入り口(診断・対話・自己紹介)には「類型論」が最強!
⚫︎ 深掘り(パーソナルプラン・採用・成長支援)には「特性論」で追い打ち!
例えるなら、
◉「タイプ論」はパッと見の“地図”
◎「特性論」はその地図を細かく測る“GPS”
アイゼンクの4気質理論とは?
元々は古代ギリシャの「四体液説(ヒポクラテス)」がルーツで、
それを心理学者ハンス・アイゼンク(Hans J. Eysenck)が、
科学的に整理し直したのがこの理論。
▼ 2軸で整理される:
- 外向性↔内向性
- 情緒安定性↔神経症傾向(不安定性)
この2軸を交差させて、性格を次の4つに分類👇
◆アイゼンクの4気質タイプ
| タイプ | 特徴 | 傾向 | ビッグファイブに例えると? |
|---|---|---|---|
| 多血質 Sanguine | 陽気・社交的・活動的 | 明るくポジティブ、おしゃべり大好き | 外向性↑、神経症傾向↓ |
| 胆汁質 Choleric | 短気・野心的・情熱的 | エネルギッシュだけどイライラしやすい | 外向性↑、神経症傾向↑ |
| 黒胆汁質 Melancholic | 内向的・繊細・真面目 | 不安が強く、完璧主義タイプ | 外向性↓、神経症傾向↑ |
| 粘液質 Phlegmatic | 穏やか・慎重・安定志向 | 落ち着きがあり、協調性が高い | 外向性↓、神経症傾向↓ |
●ざっくりイメージで捉えると…
- 多血質:クラスのムードメーカータイプ
- 胆汁質:リーダーシップあるけどキレやすいタイプ
- 黒胆汁質:心配性で真面目、職人気質
- 粘液質:控えめでやさしい、聞き役にまわるタイプ
●応用シーン
- 学生指導(今回の研究みたいなケース)
- 組織内コミュニケーションや配属
- 商品やサービス開発におけるペルソナ設計
- もちろんTOiTOiやビッグファイブとのクロス分析にも!
●補足Tips:ビッグファイブとの違いは?
- 4気質は「タイプ別(類型)」→「どの箱に近いか」
- ビッグファイブは「度合い(連続的)」→「OCEAN各要素が何点か」
つまり、
4気質は「ざっくり分けて理解する」ための地図、
ビッグファイブは「詳細に読み解く」ためのルーペって感じとなっています。
性格診断はお金がかかります。企業でも適正診断を行います。
これにも経費がかかってきます。
新潟福祉大学でもお金をできずにできる、診断ということで、アイゼンクの性格理論である、
4つの気質理論を選んでいます。
4つの質理論であれば、クロニンジャーの気質モデルがあります。
生まれ持った気質(Temperament)にあわせて「後天的に発達する性格(Character)という
統合的性格理論になっているのが大きな特長です。
今回利用されているアイゼンクは、2軸、情緒安定性↔神経症傾向(不安定性)と外向性↔内向性に整理されており、
4つの気質で構成されている極めてシンプルな類型論です。
類型論では行動の動機について知ることができます、そこに色を合わせて、
診断に膨らみを持たせていますが、個人的には、詳細は見えにくいというふうに感じます。
どんな行動傾向があるのか、周囲からどう見えるかがないため、
対策がとにくいということです。動機は理解できても、
どんな傾向があるのか、他人からどう見えるのかがわからなため、
ざっくりとしたことしか、分析できないため、立体的に視覚化できないということです。
しかし、タイプはわかるので、ある程度の対応は可能となってきます。
チーム内での役割や適材適所には向かないということがわかります。
今回は、類型論と特性論についてお話を進めました。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
大石如香・石本豪(2020). 『医療福祉を学ぶ大学生の色彩嗜好と性格特性の関連』, 2025年3月20日アクセス. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsaj/43/3+/43_169/_pdf