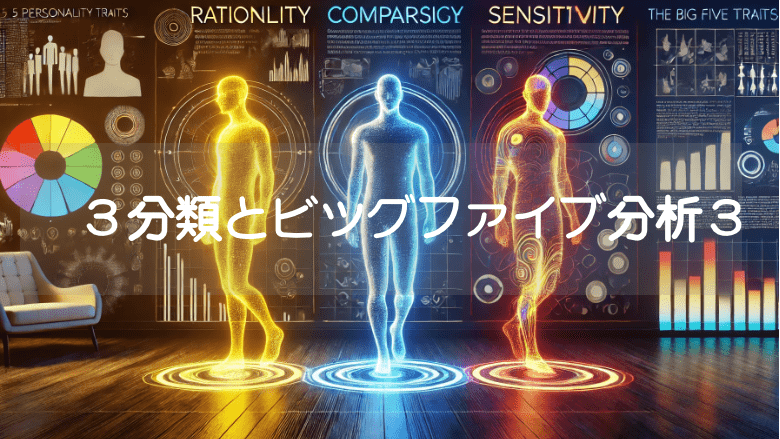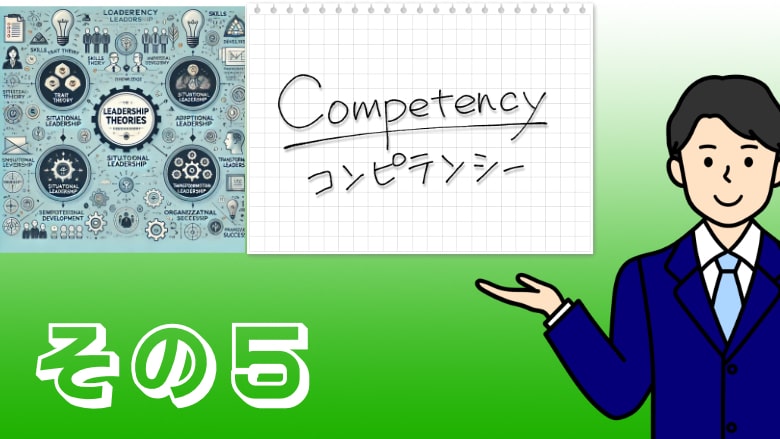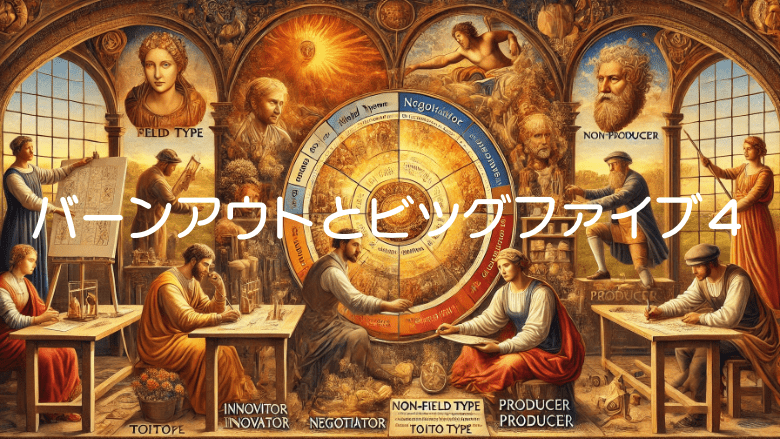日本の高校サッカーチームにおけるリーダーシップ効果とフォロワーの
性格特性の関係を調査した研究論文があります。
スポーツでもリーダーシップとフォロワーシップの関係性はあるわけです。
スポーツは試合に勝つことがまず目的です。勝利するにはメンバーの協力が必要です。
ここからチームをマネジメントするためのヒントが見つかります。
リーダーのスタイルとフォロワーの性格特性
- リーダーシップスタイル(PM理論)を基に、チームを4つのタイプ(PM, Pm, pM, pm)に分類。
- フォロワーの個人的な性格特性が、リーダーシップ効果にどのように影響するかを探っています。
PM理論の4つのリーダーシップタイプ
PM型(高P・高M)
説明: 課題達成(P機能)と集団維持(M機能)の両方で高いスコアを持つリーダー。
特徴: 成績向上とチーム内の良好な人間関係を同時に追求。
理想的なリーダーとされる。
Pm型(高P・低M)
説明: 課題達成(P機能)では高いが、集団維持(M機能)が低いリーダー。
特徴: 成績や目標達成を優先し、チーム内の対人関係の維持には関心が薄い。
管理的で厳しいスタイル。
pM型(低P・高M)
説明: 課題達成(P機能)は低いが、集団維持(M機能)が高いリーダー。
特徴: メンバー同士の関係を重視し、チームの雰囲気を良くするが、
成績や成果にはそれほどこだわらない。
pm型(低P・低M)
説明: 課題達成(P機能)と集団維持(M機能)の両方が低いリーダー。
特徴: チームの成果や人間関係に対する影響力が最も弱い。
リーダーとしての有効性が低いと評価される。
PM理論の観点からの性格特性の影響
研究調査では、フォロワーの性格特性がリーダーシップ効果を媒介する重要な要素として分析されており、
主な発見は以下の通りです。
1. 劣等感(Inferiority Scale)との関連
- 高い劣等感を持つフォロワー:
リーダーに対して親しみを感じやすいものの、不満が多い傾向が確認されました。
解釈: 劣等感が強いフォロワーは、
サポートを求めるためリーダーとの対話頻度が高まり親密度が上がりますが、
期待通りの支援が得られない場合には批判的な態度を示します。
特に「Pm型」のような管理的なリーダーに対して不満が高まりました。
2. 社会性(Sociability Scale)との関連
- 高い社会性を持つフォロワー:
リーダーとの良好な人間関係を築きやすく、
チームの維持機能(M機能)を重視するリーダー(PM型, pM型)に対する評価が高かったです。
解釈: 外向的で社会性が高いフォロワーは、
チーム内のコミュニケーションに積極的で、
リーダーの集団維持行動を重視します。
集団の一体感が形成されることで満足度が向上しました。
3. 協調性(Cooperativeness Scale)との関連
- 低い協調性を持つフォロワー:
管理的・指示的なリーダー(Pm型, pm型)への不満が高まりました。
特に技術指導が欠如した場合には批判的でした。
解釈: 協調性が低いフォロワーは、
管理的リーダーの一方的な指示に反発する傾向があります。
その結果、リーダーが部員との対話を重視しない場合、不満が増大しました。
4. 課題志向性(Task Orientation)との関連
- 課題志向性が高いフォロワー:
課題達成を重視する「PM型」「Pm型」のリーダーを好む傾向がありました。
解釈: 自己成長や競争的な環境を好むフォロワーは、
厳しい目標設定を行う課題志向型リーダーに引き付けられます。
ただし、過度な管理はストレスを生む可能性も示されました。
全体の結論と心理学的解釈
研究は、
リーダーのリーダーシップスタイルとフォロワーの性格特性が、
対人関係の質とリーダーシップ効果にどのように影響するかを多面的に分析しています。
特に、リーダーの行動がすべてのフォロワーに同様に影響するわけではなく、
フォロワー個々の性格特性によってリーダーシップ効果は大きく異なることが示されています。
- 実践的な示唆:
劣等感の強いフォロワーには支援的なリーダーシップが、
社会性の高いフォロワーには集団維持を重視するリーダーシップが適しているなど、
リーダーシップの柔軟な適用が必要だと考えられます。 - 心理学的根拠:
この研究結果は、
パーソナリティ特性がリーダーシップスタイルの効果を調整する「適性処遇交互作用(Aptitude-Treatment Interaction)」の理論とも一致し、
リーダーのスタイル選択がフォロワー特性に基づいて行われるべきであることを示唆しています。
適性処遇交互作用の構成要素
- 適性 (Aptitude):
学習者やフォロワーの持つ個人的な特性。
これには、認知スタイル、性格特性(例: ビッグファイブの次元)、
知識、スキル、モチベーションなどが含まれます。 - 処遇 (Treatment):
指導や介入の手法、リーダーシップスタイル、
教育プログラム、学習環境などがこれに該当します。
指導方法やリーダーの行動がここでの「処遇」にあたります。 - 相互作用 (Interaction):
適性と処遇の組み合わせによって成果がどのように変化するかを表します。
適性と処遇が適切に組み合わさると、
学習者やフォロワーのパフォーマンスが最大化され、
適切でない場合は成果が低下します。
適性処遇交互作用の例
1. 教育における例:
- 適性: 読解力が高い学生
- 処遇: 自由な読書プログラム(自主的な学習環境)
- 相互作用の結果: 読解力が高い学生は自由な環境で学習意欲が高まり、
学力が向上。読解力が低い学生は指導の欠如で学力が低下する可能性。
2. リーダーシップにおける例 (研究調査内容と関連)
- 適性: 社交性の高いフォロワー(外向性が高い)
- 処遇: 集団維持を重視するPM型のリーダー(支援的、対話的なスタイル)
- 相互作用の結果: 社交性が高いフォロワーは、
リーダーとの積極的な対話が増え、チーム内での満足度や成果が向上。
理論の心理学的背景
適性処遇交互作用理論は、
教育心理学者であるリー・クロンバック(Lee J. Cronbach)が1960年代に提唱しました。
彼は、「学習の個別化」の重要性を強調し、
学習者の個々の適性に応じた指導方法を開発することで、
教育の効果を最大化できると考えました。
この理論は、教育現場において「一斉指導モデル」の限界を示し、
パーソナライズされた教育や適応的学習システムの基礎となっています。
同様に、リーダーシップ理論でも、「状況適応型リーダーシップ理論(Situational Leadership Theory)」とリンクし、
フォロワーの性格特性に応じたリーダーシップ行動の必要性が示されています。
適性処遇交互作用の応用例
- 教育心理学: 学習スタイルに応じた指導法の設計(例: 個別指導、グループ学習、課題中心型学習)。
- 組織心理学: 従業員のパーソナリティや能力に応じたリーダーシップスタイルの適用。
- 臨床心理学: 患者の心理的特性に応じた治療法の選択(例: 認知行動療法 vs. 精神分析療法)。
リーダーシップ研究との関連性
研究では、フォロワーの性格特性(例: 劣等感、社会性、協調性)と
リーダーシップスタイル(PM型, Pm型, pM型, pm型)との間に有意な相互作用が確認されました。
これは、適性処遇交互作用(ATI)の理論的枠組みをリーダーシップ研究に適用した好例と解釈できます。
具体例:
- 劣等感が高いフォロワーは、支援的なリーダーシップが効果的。
- 社交性の高いフォロワーは、集団維持に注力するPM型リーダーが適している。
- 協調性の低いフォロワーには、管理的なリーダーは不適切であり、不満が増す。
このように、フォロワーのパーソナリティ特性に応じて
最適なリーダーシップスタイルを選ぶ必要があることが、
適性処遇交互作用の観点から明確になっています。
組織の運営にはフォロワーの特性により、
リーダーシップスタイルを変化させることの重要性が挙げられています。
つまり適応型リーダーシップの必要性が示されているわけです。
リーダーシップは性格特性に合わせたマネジメントスタイルを確立していくのが、
チームを活性化させるには最適であると言えるのではないでしょうか。
リーダーシップとフォロワーシップの関係性をさらに深く見ていきます。
今回はここまで。最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
伴在智秀 (1989). 『フォロワーのパーソナリティ特性の関数としてのリーダーシップ効果』, 教育心理学研究第37巻第2号, 1989年10月発行. 2024年12月22日アクセス.https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/12261
スポーツにおけるリーダーシップとフォロワーシップの関連性2へつづく