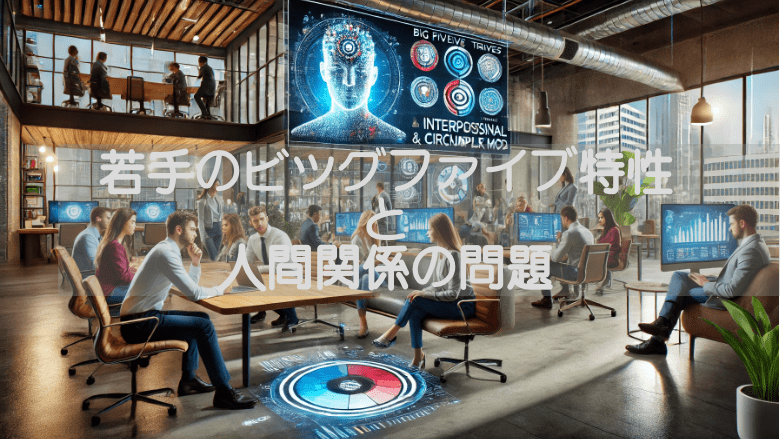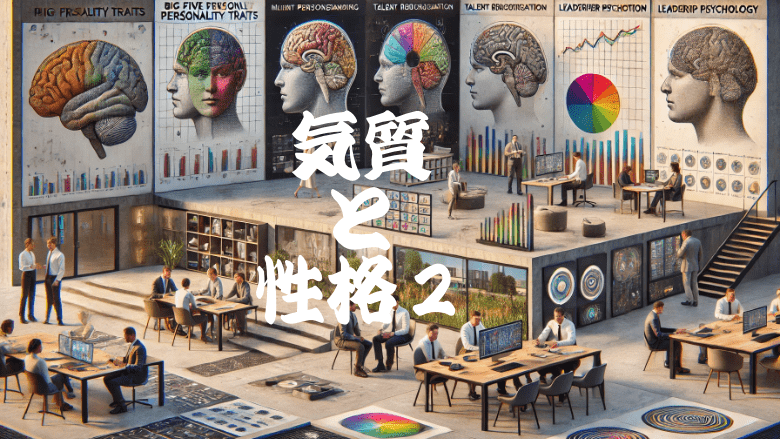![OCB[組織市民行動]:職場の環境要因と社内の協力関係6](https://i0.wp.com/master-nichen.jp/wp-content/uploads/2025/04/OCB6-min.png?fit=640%2C360&ssl=1)
前回はOSBEとTMXとビッグファイブの誠実性との関連についてお話を進めました。
ここでは採用についてお話を進めていきます。
性格分析を使った採用について
誠実性がOBSEやLMXとTMXに影響を与えるということでした。
しかし誠実性だけが助け合いが生まれるというわけではないと考えます。
だから組織に必要な人財の見極めが必要です。
TOiTOiの性格分析は組織分析も可能なツール、組織に必要な人財のタイプも把握できます。
また採用において念頭に置いておかねばならなことが、組織のパーパスやMVVです。
採用時には組織のパーパスやMVVに共感してくれる人を採用することがマストです。
なぜなら、組織の人間関係の質においてパーパスやMVVが共有されていなければ、
何のためのこの組織がある存在するという目的や会社の目標が共有されていることで、
組織内での貢献やお互いが助け合う文化が醸成され、売上や生産性向上、イノベーションが生まれる、
土壌となるからです。
ステップで考える【採用設計フロー】
Step 1|組織の“現在地”を診る(TOiTOi分析)
- 既存メンバーのTOiTOi診断を実施
- チーム内の強み・相性・足りない特性を可視化
- 例:「感性タイプ多め。比較タイプが不足」「LMXは強いがTMXが弱い」など
◼️ 目的:組織にとって「次に必要な人財の方向性」がクリアになる!
Step 2|MVV・パーパスを再定義 or 明文化
- 理念・ビジョン・大切にしたい行動規範を“言葉”として定義
- 採用候補者が共感できるように、ストーリー仕立てで発信(HP/説明会資料など)
◼️ 目的:「この会社の未来に関わりたい!」と思える仕掛けづくり
※MVVとは(ミッション・ビジョン・バリュー)
Step 3|採用時:MVV共感+TOiTOi事前診断導入
- 応募者にTOiTOi簡易版を受けてもらう
- 面談時は以下をチェック:
- MVV・パーパスへの共感度
- TOiTOiで見る「組織に足りない要素」との親和性
- 面接官と候補者の相性(関係性づくりの土台)
◼️ 目的:採るのは「スキルがある人」ではなく、「一緒に育て合える人」
Step 4|入社後の「動きたくなる環境」づくりへ連動
- TOiTOiに基づいた関わり方、1on1設計、タスク設計をカスタマイズ
- 共感からスタートしたMVVを、日常業務でもすり合わせていく
- OBSEを育てる言語化・フィードバック設計もセットで導入
◼️ 目的:入社後のギャップをなくし、「自分の居場所」→「貢献したくなる場」へ
★【MVV×TOiTOi 共鳴採用モデル】
キーワード:
- 共感から始まる共創
- スキルよりも関係性
- 採って終わりじゃなく、育てて活かす採用設計
これがOCBによる組織活性化の流れとなります。
さらに展開可能な実務ツール案
| ツール | 内容 |
|---|---|
| ◆ 採用者向け「MVV共感チェックリスト」 | 企業理念への共感度を見える化 |
| ◆ 採用担当用「TOiTOi適性評価ガイド」 | タイプ別に見る“適材適所の見極め方” |
| ◆ 面接テンプレート(MVV+TOiTOi型) | 行動エピソード+共感質問で深掘り |
| ◆ 入社後「動きたくなる環境づくりキット」 | OCBやOBSEを育てる上司用スクリプト |
などの作成をすることで、辞めたくなくなる組織、働くことが楽しい組織へと昇華していきます。
関係の質・パーパス・MVVは繋がっている
「なぜパーパスが関係性の“土台”になるのか?」
STEP 1|どんなに仲良くても、目的が違えばバラバラになる
「関係性の質がいい」とは、“仲がいい”ことではない
→ 「何のためにここにいるか」が共有されてこそ、同じ方向に向かえる
STEP 2|パーパスやMVVは、関係性の“共通言語”
誰かと違っても、同じ目的を持つと“つながれる”
→ 理念があって初めて、信頼・協力・承認が“意味を持つ”
STEP 3|「わかってもらえた(OBSE)」→「本音を言える(LMX・TMX)」→「行動したくなる(OCB)」
理念があるから「その人を信じられる」
→ 関係性が育ち
→ 自分の価値を実感でき(OBSE)
→ 自発的な貢献(OCB)が生まれる
伝え方:シンプル図解
【MVV・パーパス】
↓ (共通の意味付け)
【関係性の質】
(LMX・TMX)
↓ (安心感と承認)
【組織内自尊感情(OBSE)】
↓ (貢献したくなる内発的動機)
【OCB(助け合い行動)】
↓
【チームの成果・生産性・エンゲージメント】
OCB(組織市民行動)こそ、人的資本経営の“根幹中の根幹
なぜOCBが人的資本経営の本質なのか?
人的資本経営とは
「人」を“コスト”ではなく“価値を生み出す源泉”として捉え、
その能力・意欲・関係性・行動を“資本”として育てるマネジメント
OCBの定義(Organ, 1988)
「報酬や評価には直接結びつかないが、
組織の円滑な運営を助ける、自発的で建設的な行動」
OCB=人的資本の「質」が表れる行動そのもの
| 観点 | OCBが示すこと | 人的資本経営との接点 |
|---|---|---|
| 自律性 | 指示待ちじゃなく動けるか? | 能動的な人材像の体現 |
| 協働性 | チームにどう貢献しているか? | 組織的成果への貢献 |
| 関係性資本 | 誰かを助ける・配慮する行動 | 社内ネットワークの活性度 |
| 無形資産化 | 成果にならないけど必要な行動 | “空気・文化”の定着力 |
| 持続性 | 継続的に良い行動が起こるか? | エンゲージメントの指標 |
つまり!
人的資本=見えない資産、OCB=その動きの可視化!
経営の立場からすると、OCBは以下のように見える:
「うちの人はどれだけ“任されてなくても良い行動”を起こしてるか?」
→ = どれだけ“人という資本”が生きているか
逆に、OCBがないと…
- 指示がなければ動かない
- 他人と関わろうとしない
- 「評価されないこと=ムダ」と感じる風土
➡ 人的資本は「数字化されたスキル」だけに偏り、
“価値を生む文化資本”が失われていく…
成果主義によって起こってしまう事象が上の例です。
OCB生まれることで、人が人としての行動が取れる、
評価される行動でなくても、人としての行動がOCB。
この文化が評価される組織が今求められており、
人的資本経営の重要さが語られています。
結論
OCBは「人的資本経営が成果として現れる一番わかりやすい行動指標」。
「関係性」「エンゲージメント」「心理的安全性」などが整っていると、
人は自然に“組織のために動きたくなる”。
それを示してくれるのがOCB。
いかがでしたでしょうか。
組織が活性化するためには、成果主義により、
成果には結びつかない行動が評価されなくなりました。
そこで組織が円滑に運営されるための行動がOCBです。
それには性格だけでなく、環境が大切だということが、
研究調査で語られています。
環境と人は切っても切れません、なぜなら人は環境に左右されるからです。
私たちは自分の持っているものが活かされ、必要とされれば頑張ります、
自発的に動きます。これが本来組織のあるべき理想の姿であると、
私は考えています。
そこで環境を作るのに最適なツールがTOiTOiです。
TOiTOiは(PFのダウンロードはここから)、
Team Of Inventorhy・組織編成分析の略語で、組織の適材適所を科学的に分析し、
最適なチームをつくるツールです。
TOiTOiの由来はドイツ語で「幸運のおまじない」を意味するtoitoitoi、
相性を可視化し、働きやすい環境を実現します。✔ 強みと相性をデータで分析
✔ 生産性向上 & 離職率低減
✔ 直感ではなく科学で組織を最適化TOiTOiで、組織をもっと強く、働きやすく。
組織の関係性を高めるにはLMXやTMXで関係性を育て、
OSBEを醸成し、OCBが生まれるという流れをつくることです。
関係性の質にもパーパスやMVVが前提としてあることで、
より組織が活性化し、辞めたくなくなる組織、働くことが楽しい組織へと変化していくのです。
あなたの組織は、働くことが楽しい組織ですか。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
乗松未央・木村裕斗(2021).
『性格特性と職場環境の相互作用が若年就業者の組織市民行動に与える影響:組織内自尊感情による媒介効果に着目して』,
『産業・組織心理学研究』, 35巻2号, pp.151-166.
2025年3月23日アクセス.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaiop/35/2/35_235/_article/-char/ja/