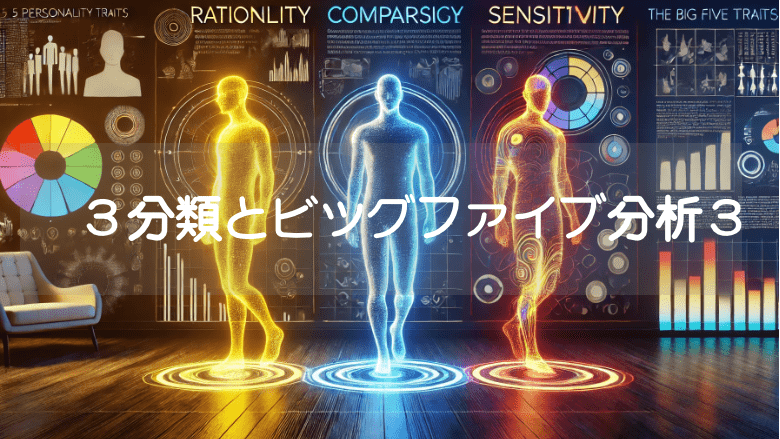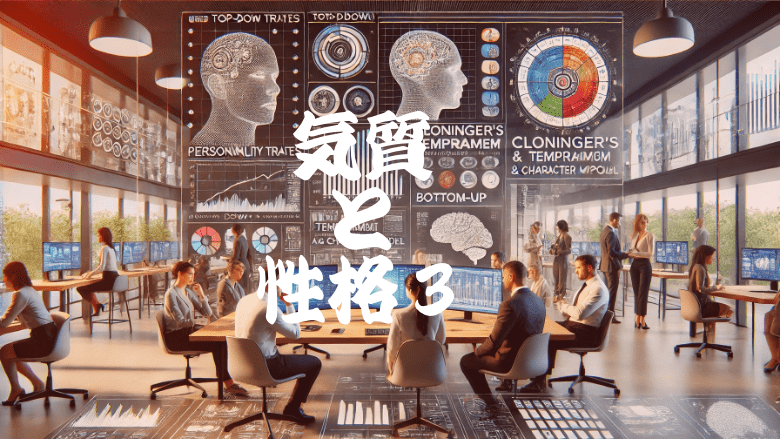![OCB[組織市民行動]:職場の環境要因と社内の協力関係4](https://i0.wp.com/master-nichen.jp/wp-content/uploads/2025/03/a796e665bb8ec629df88e84596aefbcd.png?fit=640%2C360&ssl=1)
前回はDennis W. Organ(デニス・W・オーガン)によるOCBと
George B. Graen(ジョージ・B・グレーン)によるLMXが生まれた経緯についてお話を進めました。
ここでは、OBSEとTMXについてお話を進めていきます。
OBSEとTMX
PierceとSeersが「組織内自尊感情(OBSE)」や「TMX(チーム内交換関係)」という概念を提唱した背景には、
1980年代後半のアメリカの職場文化・経営トレンドの大転換期があったんです。
【背景:1980年代後半】
キーワードは、成果主義・個人主義・グローバル競争でした。
▼ ① 成果主義の加速
- 数字で評価、KPI、アウトカムがすべて
- 個人の成果・結果ばかりが強調され、“チームや人間関係の価値”が見えづらくなっていた
成果主義により、本来は人がビジネスを動かすのですが、
その人の存在がかすみ、結果だけが評価の対象となったと言えます。
▼ ② 組織の柔軟性・自律性への要求
- 日本的経営(チームワーク・QC活動など)の良さに注目が集まる
→ 米企業でも「もっと自律的に動ける社員・チームが必要だ」との危機感がありました。
自律的な人財が必要というワードは欧米の方が気付くのが早いでね。
この差が日本がいまだに自律的な組織構築に苦しんでいるように感じます。
▼ ③ 心理学と経営学の接近
- 「人はロボットじゃない」
→ 感情や信頼関係が生産性や貢献行動にどう影響するか、を測りたい流れに。
エドモントン教授の心理的安全性や、
Googleによるプロジェクトアリストテレスが注目されてたのかもしれません。
その中で登場した2つの問い
Pierceらの問い(→ OBSE)
「なぜある人は“やらされ感”が強く、
一方である人は“自分から動こう”とするのか?」
これはよくわかる。この組織で本当に自分が必要だと感じていなければ、
人は自ら積極的には動きません。
これは私も感じたことは多々あります。
この違いは、スキルや性格ではなく──
▶︎ “その人が組織でどう扱われていると感じているか”では?
▶︎ 「私はこの組織にとって必要な存在だ」という感覚がカギでは?
➡ 組織内自尊感情(OBSE)という新しい概念が誕生
(=外から見えない“自分の価値感覚”を理論化した)
上記よりOBSEが行動(OCB)を引き出すのです。
→ 「自分は大事にされてる」→「役に立ちたい」→ OCB(助け合い行動)につながる
すごい気づきですよね。みんな言われてから『そうだよな』と気づくことを
概念として構築したことに対しては、本当に頭が下がる思いです。
Seersの問い(→ TMX)
「上司との関係性(LMX)はわかる。でも、チーム内の関係性はどう測るの?」
職場は上司だけじゃなくて、同僚との“日々のやり取り”で構成されてる。
▶︎ 「協力し合えるチームと、バラバラなチームでは、生産性に差があるのでは?」
▶︎ でもそれって、どうやって“データ”で測れるの?
➡ そこで、TMXという新しい指標を定義し、
「支援・協力・情報共有の質=チームの機能性」を可視化しようとした。
関係性の質を見える化しようとして行動に対して、感謝しかないですね。
個人的に、この考えがこれからの組織やZ世代とも向き合うヒントになると感じるからです。
今多くの企業ではZ世代と向き合おうとしていないので、
向き合えるきっかけ作りになると確信があるからです。
TMXはまとめると、
行動面: 助け合い、フィードバック、協働
感情面: 信頼、共感、安心感、所属感、
上記よりTMXは「関係性に表れる行動と感情」の両方を含む概念となるわけです。
まとめの対比イメージ
| 観点 | OBSE | TMX |
|---|---|---|
| 主な性質 | 感情・自己認知(特性寄り) | 行動+感情の混合(動機寄り) |
| 源泉 | 組織との関係性(主に上司との関係) | 同僚とのやり取り・信頼感 |
| 発揮される領域 | 自分自身の内面/自己評価 | チームとの関係/相互作用 |
| 影響する行動 | 自律性・貢献意欲・離職意向 | 協力・共有・OCB |
そして面白いのが…
両者ともに【OCB(組織市民行動)】の重要な“前提条件”になるってこと。
つまり、
- OBSEが高い → 「私はここで必要とされてる」→ 自発的に助ける
- TMXが高い → 「仲間と信頼し合えている」→ 自然と支え合う
➡ どちらも「組織に貢献する人が育つ関係性の土壌」なんです。
「わかってもらえた」=自分の存在価値が伝わっているという実感(=OBSE)
それがあって初めて、“本音”が安全に言える組織文化=心理的安全性が成立するんです。
【1】わかってもらえたという実感(OBSE)
↓
【2】安心して話せる関係性(LMX・TMX)
↓
【3】本音を発信できる心理的安全性
↓
【4】自発的な行動(OCB)が自然に起きる
という流れになります。
なぜ「わかってもらえた」が最初なのか?
- OBSEが低いと、そもそも「ここで話していいのか?」「自分なんて…」という内向き思考になりがち
- 本音を言うには「どうせ言ってもムダ」「否定されるかも」の不安が取り除かれてないと無理
- だから、“受け止められている感覚”が第一歩なんです
そして、組織としてやるべきことは…
| フェーズ | 組織でできること |
|---|---|
| わかってもらえた感の醸成(OBSE) | ✔ 1on1で貢献を明確に言語化する ✔ TOiTOiで強み・価値観を共有する |
| 信頼関係の構築(LMX・TMX) | ✔ 傾聴とフィードバックの習慣化 ✔ ペアワークや共創型プロジェクト設計 |
| 本音が言える空気づくり | ✔ 上司から「弱さを見せる文化」の実践 ✔ 本音トークの安全な場づくり(例:対話型ミーティング) |
| OCBが生まれる | ✔ 評価制度や承認文化に組み込む ✔ 小さな貢献にも光を当てる文化設計 |
結論
“わかってもらえた”と感じる組織こそ、働く人が本音で動ける組織。
TOiTOiのようなツールは、その「関係性の土台づくり」をサポートするエンジン。
TOiTOiは(PFのダウンロードはここから)、
Team Of Inventorhy・組織編成分析の略語で、組織の適材適所を科学的に分析し、
最適なチームをつくるツールです。
TOiTOiの由来はドイツ語で「幸運のおまじない」を意味するtoitoitoi、
相性を可視化し、働きやすい環境を実現します。
✔ 強みと相性をデータで分析
✔ 生産性向上 & 離職率低減
✔ 直感ではなく科学で組織を最適化
TOiTOiで、組織をもっと強く、働きやすく。
組織がうまく回るってそいういうことだったのかって気づきがたくさんありました。
普段私たちが当たり前だと思っていることが、実は当たり前でなかった。
そんなことを気づかせてもらえる内容だったのではないでしょうか。
普段は気付けることでも仕事を間に入れると、実は本当に大切なことが見過ごさせれている。
関係性もただいいというだけでなく、そこには同じ目的や目標がないと関係性がうまく気付けない。
この研究調査を読むことで、私たちは人との関係性のなかで、
自分が認められたいと思う気が無意識に働き、
相手のことが見えなくなっているのかもしれないとも感じました。
あなたなどのように感じましたか。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
乗松未央・木村裕斗(2021).
『性格特性と職場環境の相互作用が若年就業者の組織市民行動に与える影響:組織内自尊感情による媒介効果に着目して』,
『産業・組織心理学研究』, 35巻2号, pp.151-166.
2025年3月23日アクセス.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaiop/35/2/35_235/_article/-char/ja/
OCB:職場の環境要因と社内の協力関係5へつづく